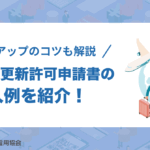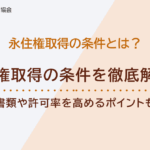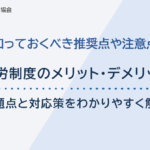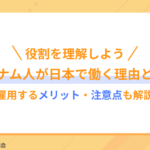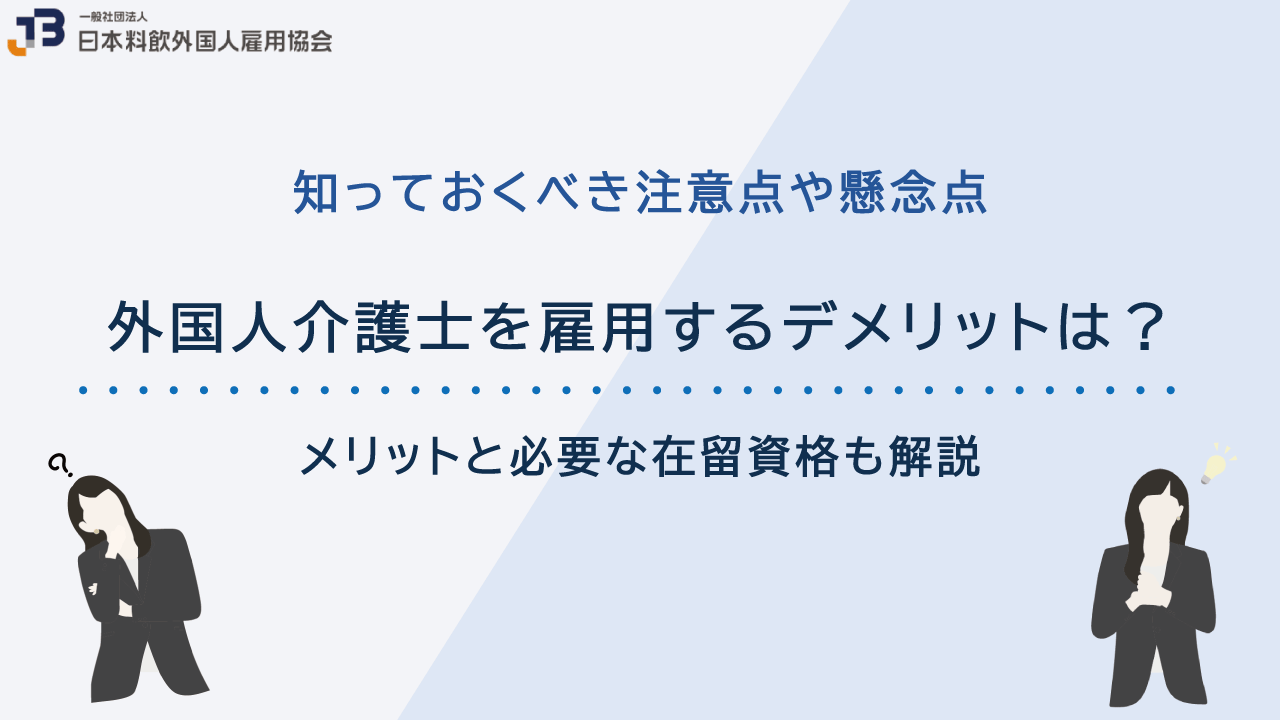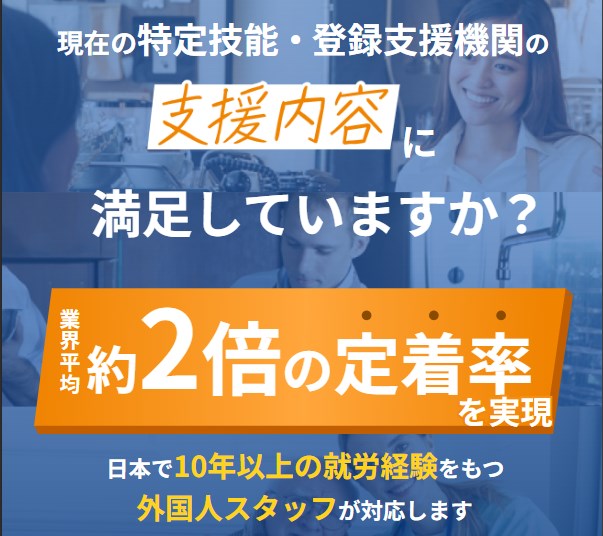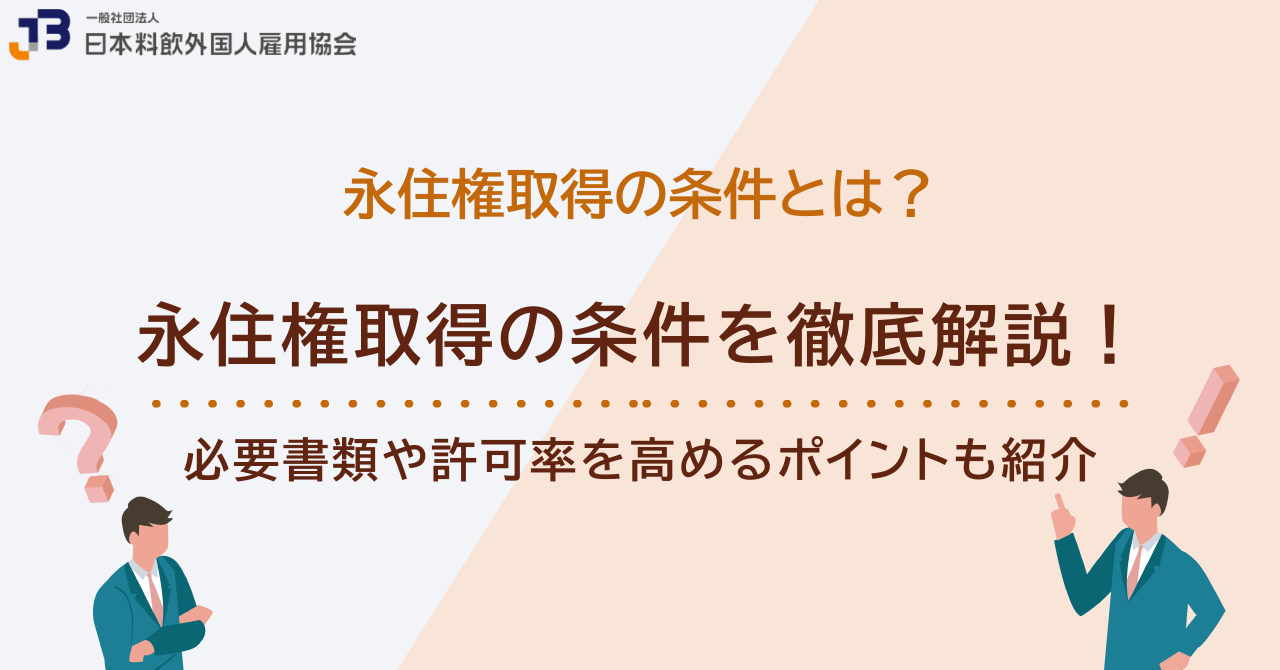「外国人介護士の採用にデメリットがあるのか知りたい」
「言葉の壁や文化の違いで、現場が混乱しないか心配です…」
このような疑問や不安を抱えていませんか?
外国人介護士の受け入れは、人手不足を補うための有効な手段として広まりつつあります。しかし、雇用後は教育の手間やコミュニケーションの難しさといった懸念点もあるのが実情です。
こうした不安を払拭するには、外国人介護士の受け入れによって起こりうる「デメリット」をあらかじめ理解し、現場で適切な準備を行う必要があります。
本記事では、外国人介護士を受け入れるうえで知っておくべき注意点や懸念点などデメリットの部分について解説します。あわせて、受け入れによるメリットや、在留資格の種類も紹介しているので参考にしてみてください。

この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
日本で働く外国人介護士の現状|受け入れ可能施設や給料事情も紹介

日本の介護業界における人材不足は深刻な課題となっています。厚生労働省の調査によると、2026年には25万人、2040年までに約57万人の介護職員が不足すると予測されています。
そこで、注目を集めているのが外国人介護士の存在です。
厚生労働省の調査で、現在日本には令和5年末時点で約28,000人の特定技能の外国人介護士が活躍していることがわかっています。また、介護の特定技能においてはベトナム・インドネシア出身者が多くを占めており、就労者は主にアジア圏出身の人材が中心です。
外国人介護士を受け入れている施設の一例は、以下のとおりです。
| 対象施設 | 施設の一例 |
|---|---|
| 児童福祉関連 | ・児童発達支援 ・放課後デイサービス ・児童発達支援センター |
| 障がい者関連施設 | ・短所入所 ・共同生活援助(グループホーム) ・福祉ホーム |
| 老人・介護関連施設 | ・老人デイサービスセンター ・特別養護老人ホーム ・老人短期入所施設 |
| 生活保護関連施設 | ・救護施設 ・更生施設 |
| その他の社会福祉施設 | ・地域福祉センター ・ハンセン病療養所 ・労災特別介護施設 |
参考:厚生労働省|技能実習「介護」における固有要件について
給与は日本人と同等以上であることが法律で定められています。しかし、都市部では比較的給与が高くされている一方で、地方では給与水準が低い状況です。外国人介護士は、今後さらに重要な役割を担うとされています。
 猪口 裕介
猪口 裕介安定的な雇用には、給与面や労働環境、語学や文化への支援など多方面でのフォローが不可欠です。
外国人介護士を受け入れるデメリットや問題点


介護現場の人手不足を支える存在として注目される外国人介護士ですが、言葉の壁や日本の文化への適応など課題もあります。
外国人介護士を受け入れる際のデメリットや問題点は、以下の3つです。
- 受け入れや教育に時間がかかる
- 帰国してしまう可能性がある
- コミュニケーション面で苦労するケースがある
外国人介護士を積極的に受け入れるためにも、注意すべきポイントをあらかじめ理解しておきましょう。
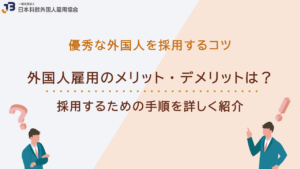
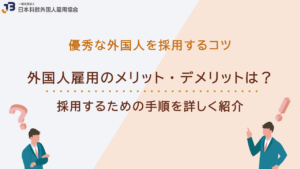
受け入れや教育に時間がかかる
外国人労働者は日本人とは異なり、在留資格の手続きや生活面のサポートなど、受け入れにあたって施設側の負担が大きくなってしまいます。
とくに教育や指導の面では、日本語での業務理解に時間がかかり、日本人よりも人材育成に遅れが生じる可能性があります。
主な注意点は、以下のとおりです。
- 専門用語や敬語など日本語能力に個人差がある
- 職員や利用者とのコミュニケーションに壁が生じることがある
- 育成スピードに差があり継続した支援が必要になる
意欲的に学ぶ姿勢を持って来日する外国人労働者が多いです。そのため、施設側が適切な体制を整えることで、着実に戦力として活躍してくれる可能性が高まります。
「外国人に教育・研修する際のポイントが知りたい!」という方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人教育の基本原則
- 在留期間における教育ロードマップ
- 実践的な教育のコツ
- よくある失敗例と対策 など
帰国してしまう可能性がある
在留資格の種類によっては、外国人が帰国してしまう可能性があります。
例えば「技能実習」の在留資格は、日本技術の国際貢献が目的なので、実習後は帰国が前提となっています。そのため、戦力となった時期に帰国してしまうケースも少なくありません。
外国人を長期雇用したい場合は、帰国する可能性が低い在留資格を持つ外国人を受け入れる視点も大切です。
コミュニケーション面で苦労するケースがある
日本語や文化に慣れていない外国人介護士とのコミュニケーションは、業務の中で行き違いや誤解を生む可能性があります。
以下は起こりうる問題の例です。
- 利用者に適切な言葉をかけられない
- 専門用語を使った会話が理解できない
- 必要な情報が正確に伝わらずケアに支障をきたす
- 利用者や職員との日常会話が難しく信頼構築が進まない
利用者やその家族、職場の従業員との円滑な関係構築のためにも、日本語学習のフォローが必要不可欠です。


「外国人介護士への理解をさらに深めたい」という方に向けて、外国人従業員との円滑なコミュニケーション術の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
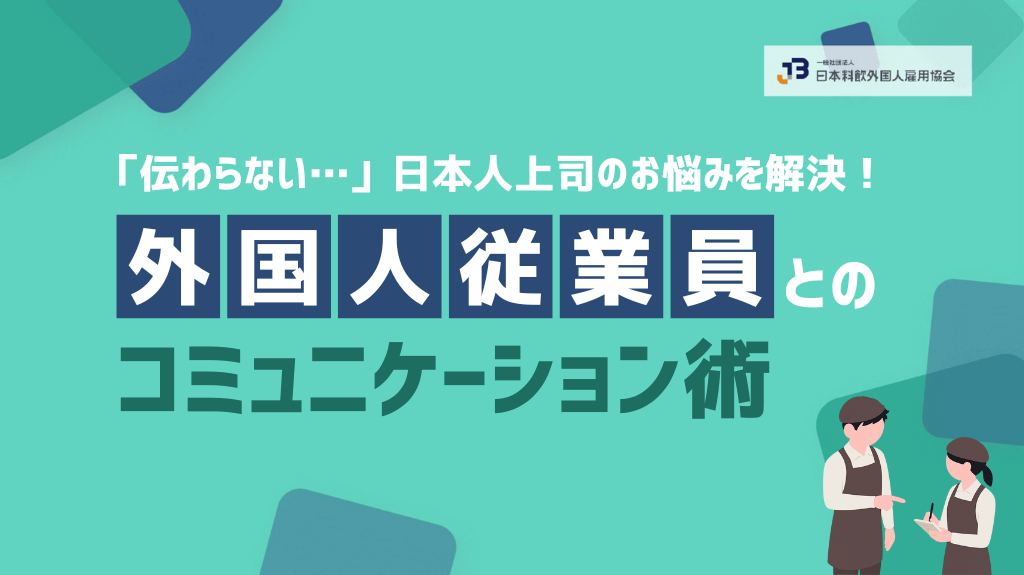
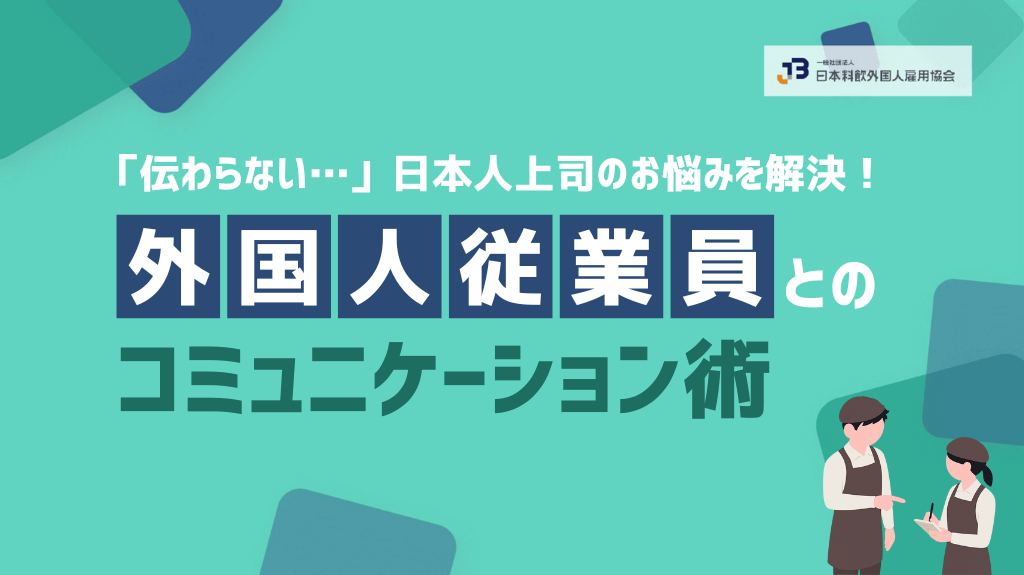
この資料でわかること
- 異文化コミュニケーションの基礎
- 文化の違いや言語の壁を乗り越えるコツ
- 効果的なコミュニケーション方法
- コミュニケーション改善の実践例 など
外国人介護士を受け入れるメリット


外国人介護士の受入れにはデメリットもありますが、人手不足の解消や職場の活性化といったメリットも期待できます。
外国人介護士を受け入れる主なメリットは、以下の3つです。
- 人手不足解消が期待できる
- 職場の雰囲気が明るくなる
- 働く意欲が高い人材を採用できる
順番に見ていきましょう。
人手不足解消が期待できる
厚生労働省の発表によると、令和4年2月時点で介護サービスの有効求人倍率は3.55と、日本人労働者だけでは人手不足を解消できていないのが現状です。
外国籍人材を受け入れることで、これまで接点のなかった外国人にも求人情報が届きやすくなり、応募者数の増加が見込めます。従来の採用活動だけでは難しかった人手不足の解消にも効果的です。
また、外国人労働者は20〜29の年齢層がもっとも多く、体力を必要とする介護業務でも安定した雇用が見込めます。地方であっても、条件次第では労働力を確保可能です。
外国人介護士の受け入れによって人手不足が緩和されると、現場の業務負担が分散され、職員一人あたりの労働量が軽減されます。



その結果、介護業界全体が働きやすい環境へと改善されることが期待できます。
職場の雰囲気が明るくなる
外国人介護士を受け入れることで、国籍を越えた職員同士の交流が活発になります。異なる文化や価値観を持つスタッフ同士が関わることで、どうすれば伝わるのかといった視点が生まれ会話の機会が増えます。
外国人介護士が職場にいるメリットは、以下のとおりです。
- 教育や支援方法に関する話し合いの機会が増える
- 対話を通して、お互いの価値観や文化への理解が深まる
- 新しい環境で頑張る姿を目の当たりにし、刺激になる
外国人介護士の受け入れは単なる人員確保に留まらず、職場全体の活性化と意識改革を促すキッカケにもつながります。
働く意欲が高い人材を採用できる
外国人労働者の多くは、家族を支えたい、学んだ知識を母国で活かしたいなど、前向きな理由で来日しています。明確な目標を持って来日するため、外国人介護士はモチベーションの高い点が特徴です。
以下のように、業務に真面目に取り組む傾向が強いです。
- 新しい仕事を覚えることに興味がある
- サービス精神が豊富で思いやりがある
- 真面目でスキルアップにも意欲的に取り組む
適切なサポート体制を用意すれば現場の即戦力として活躍し、将来的にはチームの中核を担う職員へと成長することも十分期待できます。
日本で働く外国人介護士に必要な在留資格


外国人労働者が介護士として働く場合、在留資格が必要です。それぞれの制度には、取得条件や就労期間、更新要件などが定められており、採用する施設側も内容を理解しておかなければいけません。
介護分野で働くために利用できる在留資格は、以下の4つです。
- 特定活動「EPA(経済連携協定)」
- 在留資格「介護」
- 技能実習
- 特定技能1号
それぞれの在留資格の違いを、詳しく解説していきます。
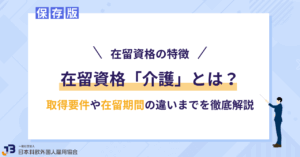
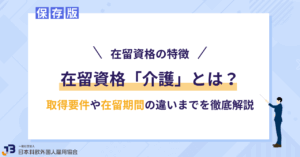
特定活動「EPA(経済連携協定)」
日本は経済連携協定(EPA)に基づき、2008年からインドネシア、2009年にフィリピン、2014年にはベトナムと協定を結び、介護人材の受け入れを開始しました。
EPAの目的は人手不足の解消ではなく、経済関係の強化です。
EPAで来日する外国人は、最長4年間の滞在中に介護福祉士国家試験の合格を目指します。母国で一定の資格や経験を持つ人材が対象で、日本でもすぐに現場での活躍が見込まれます。



国家資格取得後に在留資格「介護」へ移行することで、継続的な就労が可能です。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は2017年に創設された制度で、日本国内で介護福祉士として働くことを希望する外国人に向けた在留資格です。
日本の介護福祉士養成施設を卒業し国家試験に合格すれば、卒業後も介護職として働けるようになりました。
2020年4月からは制度の対象が拡大され、介護施設などで3年以上の実務経験を積み、国家資格を取得した外国人も「介護」ビザへの切り替えができます。
国家資格に合格する必要があるため、高い日本語能力を備えているケースが多いです。また、在留期間の更新回数制限もないため、長期的な雇用や指導的役割も期待される人材です。
技能実習
介護分野の外国人技能実習は、2017年に開始された制度です。発展途上国の人材が日本の介護現場で技術を学び、母国の発展に活かすことを目的としています。
最長5年の在留が可能です。「技能実習」修了後は「特定技能1号」への移行も認められており、最大10年間在留できます。
介護分野の実習では入国時に日本語能力N4、2年目以降にはN3相当の語学力が求められます。
特定技能1号
特定技能1号は、2019年に深刻化する人手不足への対応策として創設された制度です。特定の分野において一定の技能や知識を持つ外国人材の受け入れが可能で、介護分野もその対象のひとつです。
2025年には制度改正により、訪問介護サービスの従事も可能になりました。
特定技能1号で介護職として働く外国人は、原則として最長5年間の在留が認められ、さらに働く場合は在留資格を「介護」に切り替えなければいけません。
「介護現場における外国人材導入の重要ポイントを知りたい!」という方に向けて、特定技能制度 訪問介護解禁 導入スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 訪問介護解禁の背景・概要
- 外国人材・事業者における要件
- 訪問介護における外国人材の受入れ手続き
- 訪問介護に外国人材を導入するメリット など
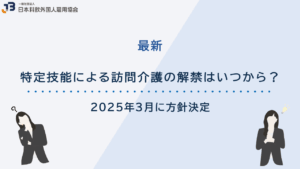
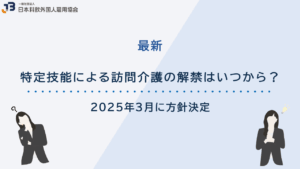
外国人介護士をスムーズに受け入れるコツ


外国人介護士の受け入れには、在留資格の手続きや教育体制の整備など慎重な準備が必要です。現場で長く安心して働いてもらうためには、スムーズな受け入れ体制の構築が欠かせません。
在留資格によって受け入れまでの流れは違いますが、スムーズに受け入れるコツは、以下の3つです。
- 人材紹介会社を利用して外国人労働者を探す
- 雇用手続きを専門家に依頼する
- 就労支援を外部機関に委託する
順番に解説します。
人材紹介会社を利用して外国人労働者を探す
希望に合った外国人介護士を雇用する際は、人材紹介会社の利用がおすすめです。人材を紹介してもらえるほか、求職者とのやりとりも代行してもらえるため、自社の負担が軽減されます。
人材紹介会社の中でも、外国人向けの支援に強い会社を選びましょう。理由は以下の3つです。
- 定着支援のノウハウが豊富
- 在留資格や法的手続きに精通している
- 外国人材の特性や文化的背景を理解している
専門性の高い人材紹介会社を選べば、優秀な外国人介護士に出会える可能性が高まります。
雇用手続きを専門家に依頼する
スムーズな外国人雇用を実現するなら、雇用手続きを専門家に依頼しましょう。
外国人の公的手続きを代行できる専門家は、申請取次の資格を持つ行政書士が該当します。
申請取次行政書士に依頼するメリットは、以下のとおりです。
- 法改正への対応が確実
- 申請手続きの時間短縮が可能
- 複雑な書類作成を代行してもらえる
専門家に依頼することで、企業は本業に集中でき、外国人材も安心して日本での就労を開始できる環境が整います。
どのような行政書士と契約すべきか悩んだら「FES行政書士法人」に相談するのがおすすめです。FES行政書士法人は、外国人就労者・海外人材に特化した行政書士法人です。
豊富な実績と専門知識で、外国人雇用を総合的にサポートしています。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから


就労支援を外部機関に委託する
在留資格によっては就労支援が義務化されています。
例えば「特定技能」の在留資格を持つ外国人を雇用する場合、受け入れ企業は支援計画書の作成と義務的支援の実施が法律で定められています。
特定技能の就労支援においては「登録支援機関」の外部機関に委託が可能です。自社だけの対応が難しいと感じたら、外部機関への委託も積極的に検討しましょう。


外国人介護士の受け入れをご検討中なら当協会にご相談ください
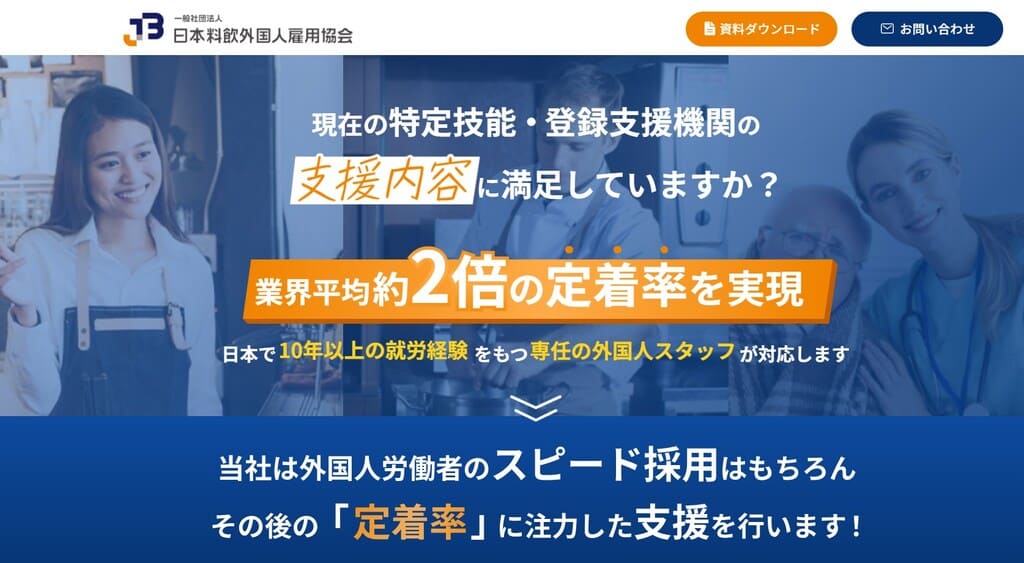
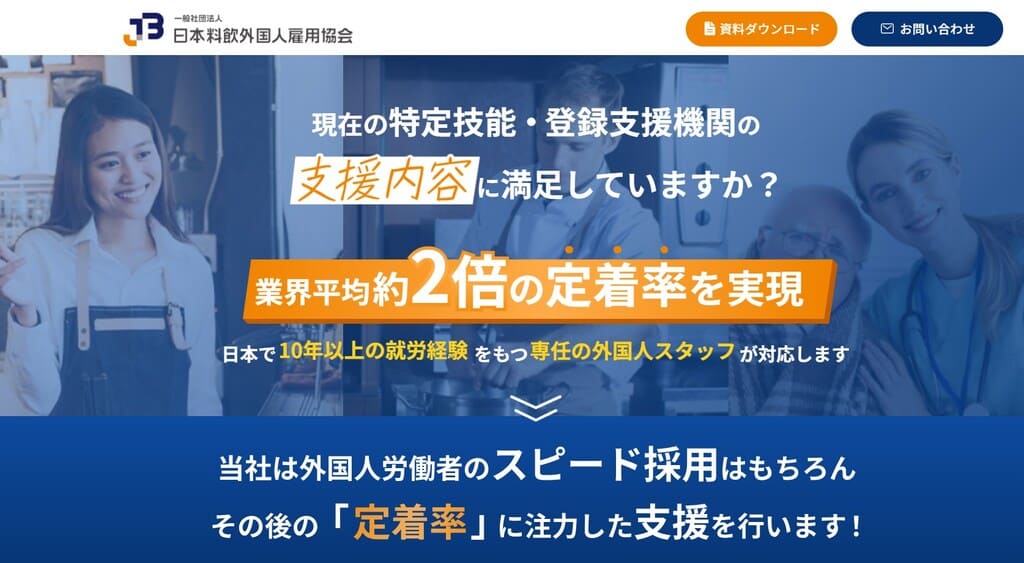
「外国人介護士を雇用したいが、自社で手続きを進められるか不安…」
このようにお悩みなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護分野の就労支援に強い外国人向けの人材会社です。登録支援機関としての認定も受けており、多くの外国人介護士の支援をしてきた実績があります。
介護現場での定着を意識し、生活面の不安を解消できるよう、住居探しのサポートや地域の生活情報を母国語での案内も可能です。単なる法定支援を超えた細やかな対応により、外国人介護士が安心して働ける環境づくりに努めています。
「FES行政書士法人」と連携し、在留資格の申請や更新などの法的手続きもスムーズに進められます。
無料相談を受け付けているので、外国人介護士の受け入れをご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
外国人介護士を受け入れるデメリットを理解したうえで雇用を検討しよう


外国人介護士の受け入れには、言葉の壁や教育体制の構築に手間がかかるといったデメリットがあります。
しかし、将来的には施設にとって欠かせない戦力へと育ってくれる可能性があるため、受け入れるメリットも大きいです。
本記事で紹介した受け入れのポイントや支援方法を参考に、外国人介護士の雇用をぜひ検討してみてください。
とはいえ「自社で専門的な手続きや外国人のフォローができるか不安…」と感じる方もいるでしょう。
このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護分野の就労支援に強みを持ち、外国人の採用から定着支援に注力しております。外国人の中でも、日本語能力や人柄、意欲に優れた人材の確保にこだわり、ミスマッチの少ない採用を実現しています。また、行政書士法人と連携しているため、法的手続きもスムーズに対応可能です。
無料相談を受け付けていますので、外国人介護士の採用でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿