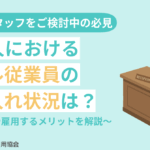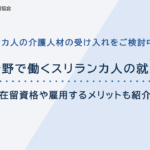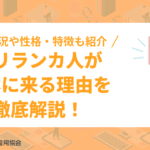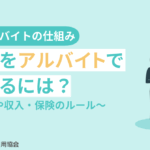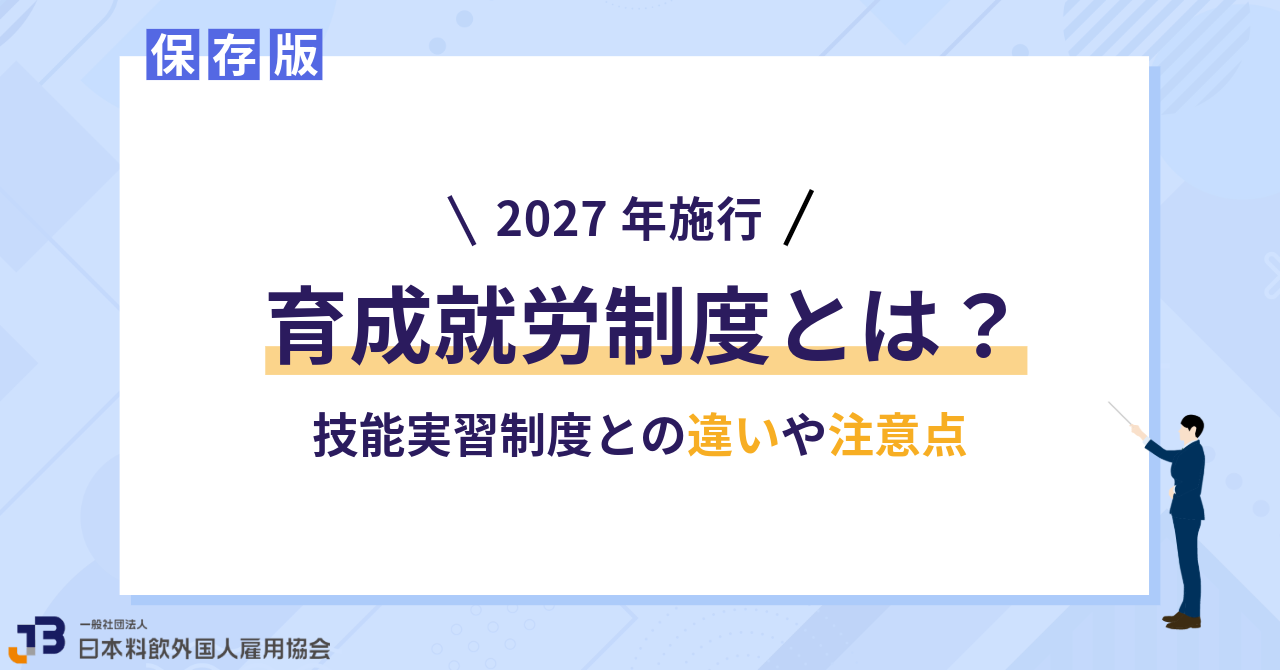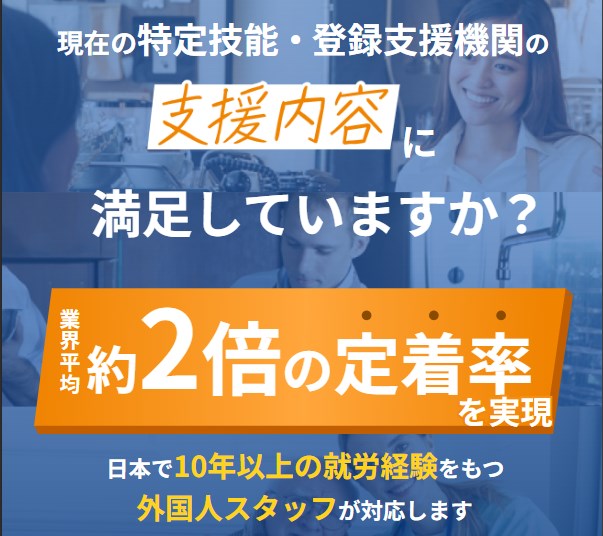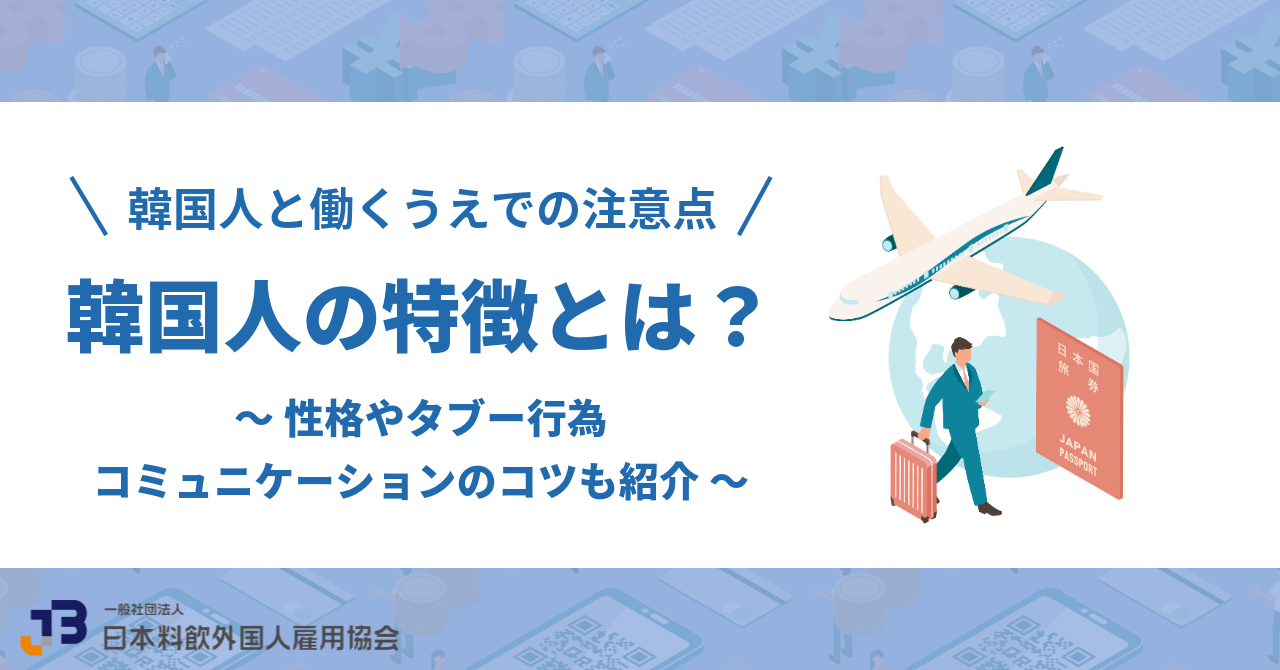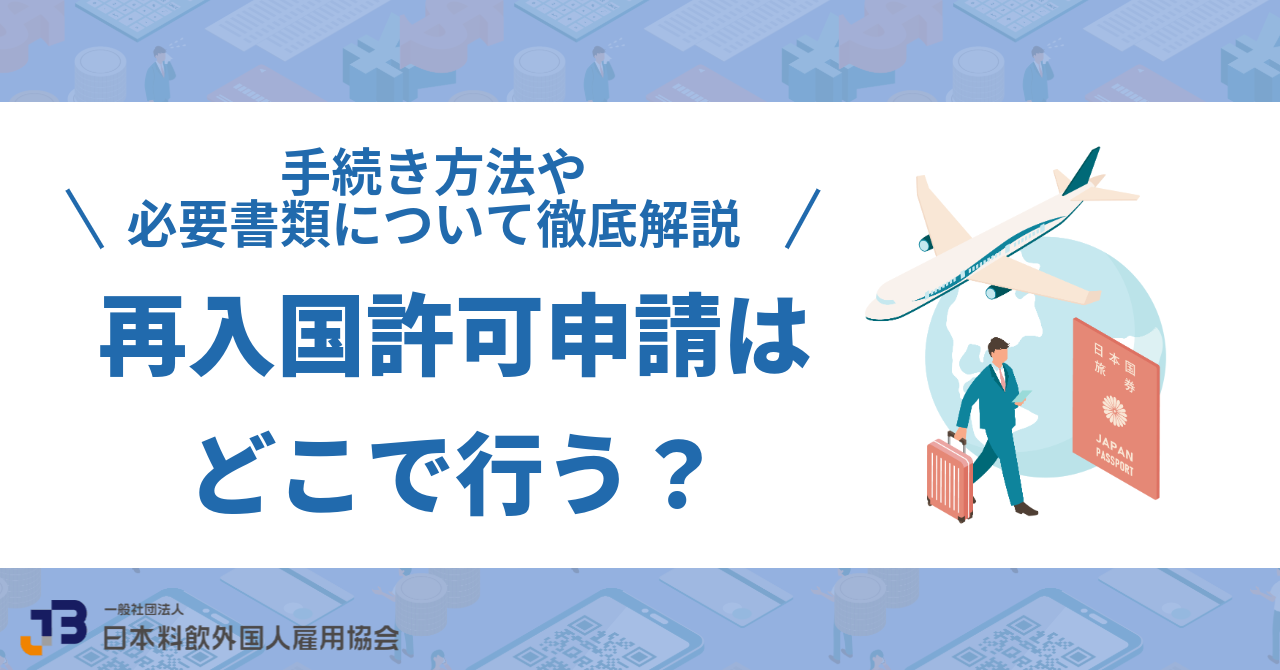「育成就労制度はどんな制度?」
「現行の技能実習生制度からの変更点はある?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
育成就労制度とは、外国人の人材確保と人材教育を目的とした制度です。現行の技能実習生制度が廃止され、新たに施行されます。外国人労働者の人材確保に役立つ制度なので、外国人雇用を検討している方は理解を深めておきましょう。
本記事では、育成就労制度について詳しく解説します。技能実習生制度の違いや注意点も紹介しているので、参考にしてみてください。
【基礎知識】育成就労制度とは
育成就労制度とは、外国人労働者の人材確保と人材育成を目的とした制度です。現行の技能実習制度が廃止され、新たに施行されます。
この制度は、外国人が日本企業で3年の教育期間を経て、専門的な技能を有する「特定技能」の労働者として活躍できるスキルや知識を習得させる仕組みです。以下2つの視点から、育成就労制度についてさらに深掘りしていきましょう。
- 育成就労制度はいつから施行される?
- 技能実習生制度が見直された背景
順番に解説します。
育成就労制度と技能実習制度の変更点が気になる方は育成就労制度と技能実習生制度の違い【大きな変更点は5つ】をご覧ください。
育成就労制度はいつから施行される?
育成就労制度は、2024年6月14日の参議院本会議で可決・成立しました。2025年3月11日に基本の運用方針が閣議決定され、2027年6月までに施行されると見込まれています。
 猪口 裕介
猪口 裕介3年ほどの準備期間が設けられているため、現行の技能実習制度からの移行をスムーズに進められます。
技能実習生制度が廃止される理由
技能実習生制度では、以下のような課題がありました。
- 監理団体による不適正な受け入れが発生
- 転籍が制限され労働者としての権利保護が不十分
- 実習終了後は帰国する仕組みによりキャリアパスが不明確
こうした問題により、外国人の失踪や日本の雇用環境のイメージダウンにつながっています。新しく育成就労制度を設立し、課題改善と支援の充実を図ることで、外国人労働者が働きやすい環境を整えました。
育成就労制度と技能実習生制度の違い【大きな変更点は5つ】
育成就労制度と技能実習生制度の違いを以下の表にまとめました。変更点は、大きく分けて5つです。
| 項目 | 育成就労制度 | 技能実習生制度 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 人材育成・人材確保 | 国際貢献 |
| 受け入れできる職種 | 特定技能と同じ16分野 | 90種類165作業 |
| 転籍の権利 | 制限の緩和 | 制限が厳しい |
| 就労開始時点の日本語能力 | 日本語能力試験N5レベル | 要件なし |
| 管理・支援体制 | 機関の要件が不明確 | 機関の要件を適正化 |
順番に見ていきましょう。
1.制度の目的
技能実習生制度の目的は「国際貢献」です。日本の技術を外国人に習得させ、国際社会の経済や課題解決に役立てる狙いがあります。



制度の性質上、就労前の育成期間が終了したら、外国人は帰国するのが前提です。
育成就労制度では、目的が「人材確保」と「人材育成」になりました。日本は産業全般で労働者が人手不足です。日本の労働市場のニーズに合わせて目的が変更されました。
2.受け入れできる職種
制度を利用しての就労には、受け入れできる職種に制限があります。
技能実習制度は、90職種165作業と幅広い分野での受け入れが可能です。一方で、育成就労制度では、特定産業分野と原則一致が義務付けられ、以下の16分野に限定されます。「産業のカテゴリー」に該当しない職種には、外国人は就労できません。
| 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業を統合)、建設、造船、舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造、外食、林業、木材産業 |
育成就労制度に移行に伴い、技能実習2号対象職種のうち、特定産業分野があるものは受け入れ対象として検討されています。



ただし、今後の政策変更や労働市場の需要に応じて、職種が追加される可能性もあります。
3.転籍の権利
現行の技能実習制度では、契約中の企業に不満があったとしても、原則として別の企業に転籍できません。



このような「逃げられない環境」が、外国人失踪の一因となっています。
育成就労制度では、「暴行や各種ハラスメント」「法令・契約違反行為」といった、やむを得ない場合の転籍が認められやすくなるように制度が見直される予定です。
また、以下の条件を満たせば、本人の意向による転籍が可能になりました。
- 同じ業務の区分内である
- 技能検定試験の基礎級を合格する
- 同一機関での就労が1〜2年を超えている
- 日本語能力に係る試験(A1~A2相当)を合格する
- 転籍先が、育成就労を適正に実施する基準を満たしている
外国人の権利が保護され、働きやすい環境が少しずつ整備されています。
4.日本語能力の要件
育成就労制度では、外国人に対して日本語能力の要件が追加されました。就労前までに、以下のいずれかの要件を満たすことが求められます。
- 日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)に合格
- 認定日本語教育機関等において上記に相当する日本語講習を受講
要件を満たすために、受け入れ企業は外国人への日本語学習サポートを視野に入れる必要があります。
5.管理・支援体制
制度の変更に伴い、管理・支援体制も変わります。
現行の技能実習制度では「監理団体」が外国人の受け入れの支援をおこなっています。しかし、機関の要件が明確に定まっていなかったため、不適切な受け入れや支援の事例が発生していました。
育成就労制度では、監理団体に代わる「監理支援機関」が確立されます。監理支援機関の独立性・中立性を確保するため、要件を適正化しました。



これにより、正当な受け入れ体制の構築が期待されます。
外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」も新たに設立されました。特定技能外国人への相談援助業務が加わり、外国人労働者の支援・保護の機能が強化されています。
なお、支援業務の委託先は登録支援機関に限定されます。
▼登録支援機関に関する記事リスト
「特定技能外国人への理解をもっと深めたい!」という方に向けて、特定技能制度まるわかりガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
育成就労制度における事業主側の3つの注意点
育成就労制度における事業主側の注意点は、以下のとおりです。
- 採用コストがかかる
- 条件や労働環境が悪いとすぐに辞められてしまう
- 日本語学習のサポートが求められる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.採用コストがかかる
採用コストの検討は、育成就労制度に取り組むうえで避けて通れません。
以下は、育成就労制度で外国人を雇用する際に発生する費用例です。
- 渡航費
- 交通費
- 日本語学習費
- 受け入れ体制の整備
- 送り出し機関への手数料
負担額は外国人材の出身地や支援内容により異なりますが、初期費用だけで1人あたり約50万円以上となる場合があります。
制度を活用して外国人を受け入れるなら、採用コストを含む適切な予算を確保しておく必要があります。
2.条件や労働環境が悪いとすぐに辞められてしまう
育成就労制度では転籍が可能になるため、条件や労働環境が悪いと外国人が早期離職するリスクが高まります。転籍を防ぐためには、外国人にとって魅力的な労働環境を整えましょう。
- 外国人が過ごしやすい雰囲気を作る
- 外国人向けの福利厚生を充実させる
- 給料水準をほかの従業員と同等にする
外国人の視点に立った環境を整えれば、定着率が向上します。
「外国人を雇用する際の労働条件についてくわしく知りたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
3.日本語学習のサポートが求められる
育成就労制度では、就労前までに、A1相当以上の日本語能力の習得が求められています。そのため、企業側でも外国人の日本語学習をサポートする必要があります。
- 専属の教育者を配属
- 社内で日本語講座を開催
- オンライン学習ツールの提供
日常のコミュニケーションを大切にするのも、日本語力向上につながります。
「日本語学習の支援に役立つ教育のコツがを知りたい!」という方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人教育の基本原則
- 在留期間における教育ロードマップ
- 実践的な教育のコツ
- よくある失敗例と対策 など
育成就労制度の移行にお悩みなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください
「旧制度からうまく移行できるか不安」
「日本語のサポートまで手が回らなそう」
「すぐに転籍されたらどうしよう」
育成就労制度の活用に関して、このような不安をもった方もいることでしょう。育成就労制度に関してお困りの際は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、外国人労働者の雇用サポートをおこなっている登録支援機関です。育成就労制度に詳しい外国人スタッフが多数在籍しているため、企業と特定技能1号に移行した外国人双方に適切な支援が提供できます。
- 制度に関する質問に的確な回答
- 外国人に日本語学習機会の提供
- 就職後も母国語スタッフが支援者をフォロー
きめ細やかなサポート体制により、外国人労働者の定着率は業界平均の約2倍を実現しています。無料相談も受け付けているので、育成就労制度を活用した外国人雇用を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
育成就労制度に関するよくある質問
育成就労制度に関するよくある質問をまとめました。
育成就労制度にデメリットはありますか?
育成就労制度には、以下のようなデメリットがあります。
- 採用コストがかかる
- 受け入れ可能な職種が減る
- 好条件の企業に人材が流れる
育成就労制度は、外国人労働者の人材確保に効果的な制度です。メリット・デメリットを知ったうえで、制度の利用を検討しましょう。
育成就労制度は、特定技能制度と何が違いますか?
育成就労制度は育成を重視していますが、特定技能制度は専門性や技能をもつ「即戦力となる人材」かどうかを重視している点が違います。
また育成就労制度の在留期間は原則3年、特定技能1号は5年を上限とする在留が可能です。


育成就労制度を理解して自社が求める外国人を雇用しよう
技能実習制度の認識のままで、育成就労制度を利用すると企業側がリスクを負う可能性があります。リスクを回避するためにも、本記事で紹介した変更点や注意点をよく理解しておきましょう。
- 採用コストがかかる
- 条件の良い企業に人材が流れる
- 日本語学習のサポートが求められる
「内容は理解できたけど、自社で適切に対応できるか不安…」という方は弊社「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は外食・宿泊業界に特化した、業界初の登録支援機関です。累計335社の企業様に対し、外国人材の就労を支援してきた豊富な実績とノウハウで業界平均の約2倍という高い定着率を達成しています。
弊社には育成就労制度に詳しいスタッフが在籍しています。外国人労働者に対して日本語学習機会の提供や母語を話せるスタッフによる継続的なフォローなどの充実したサポートの適正価格での提供が可能です。
無料相談を受け付けていますので、育成就労制度で特定技能1号の人材確保を検討している方はお気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿