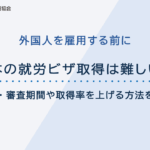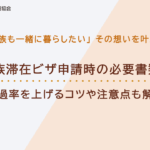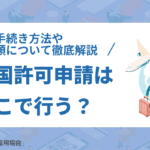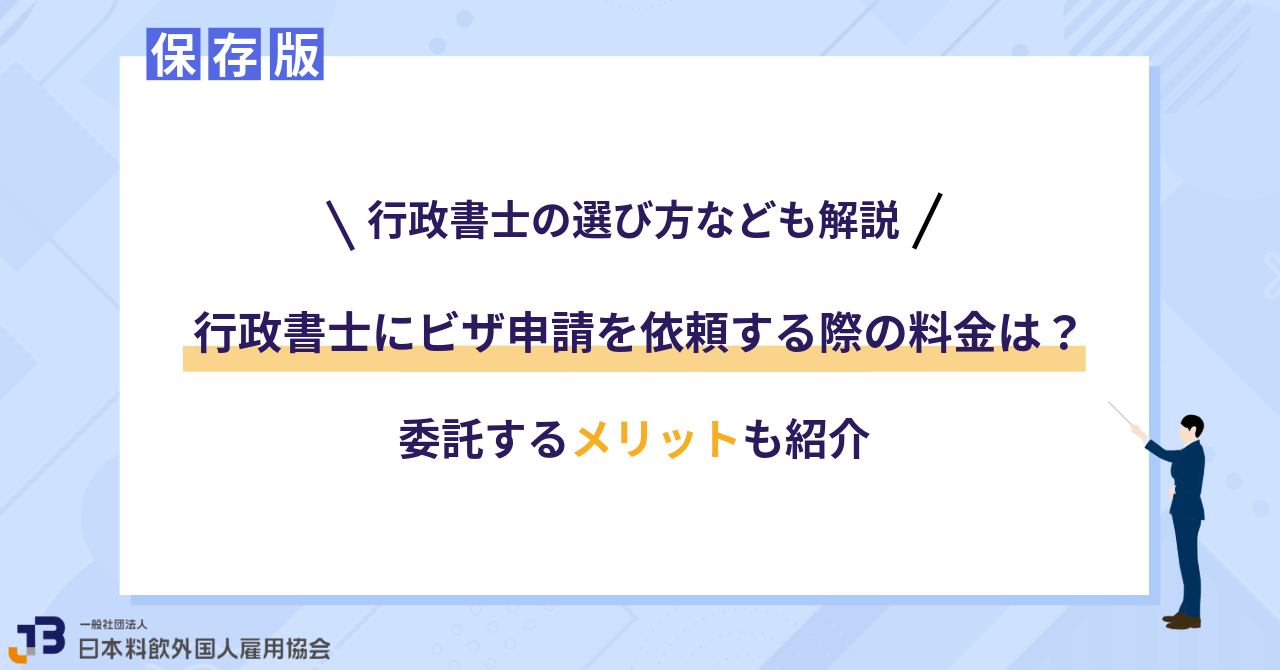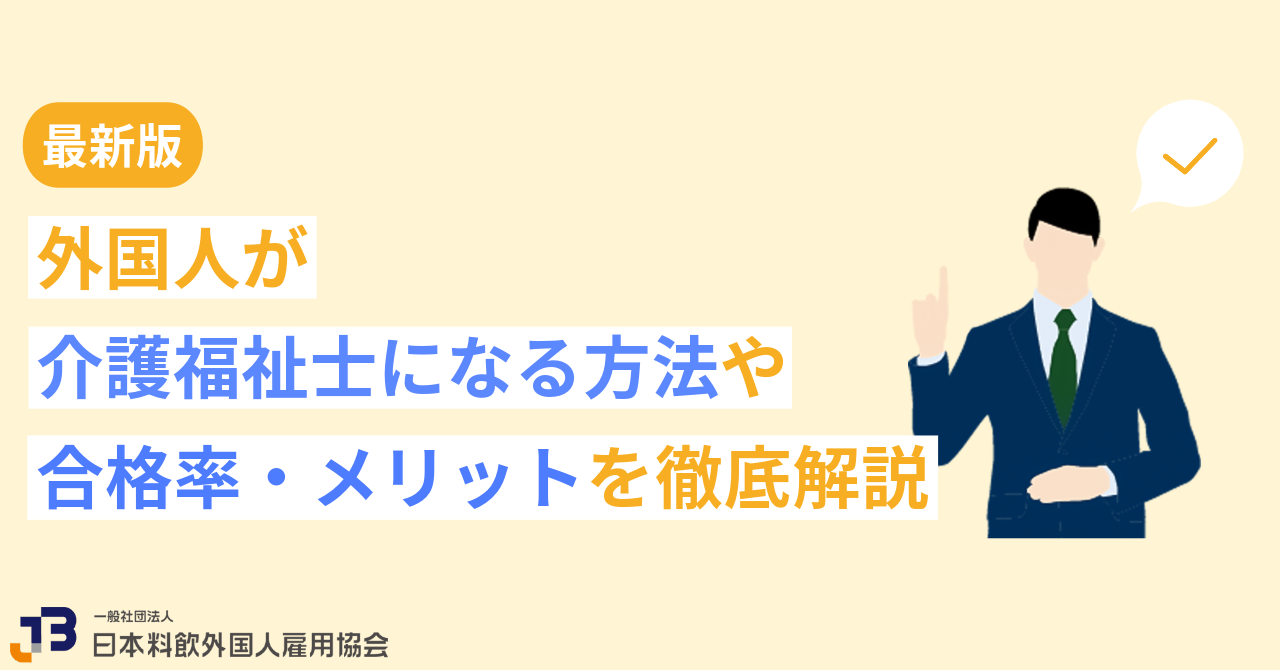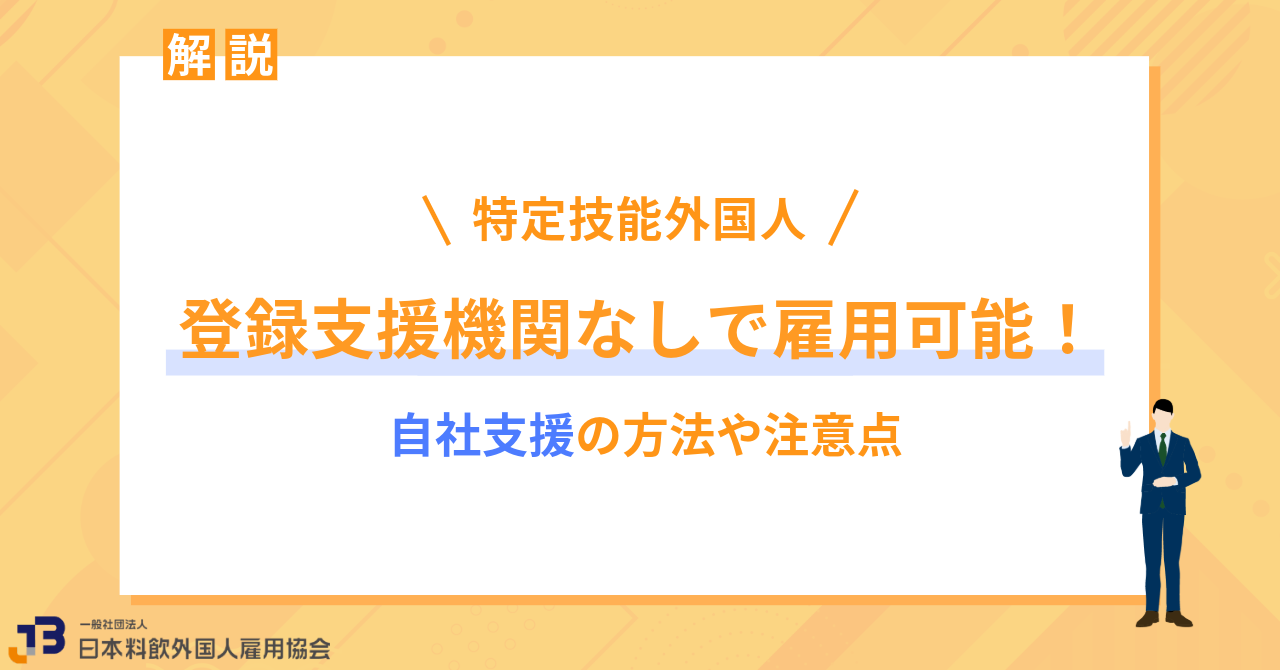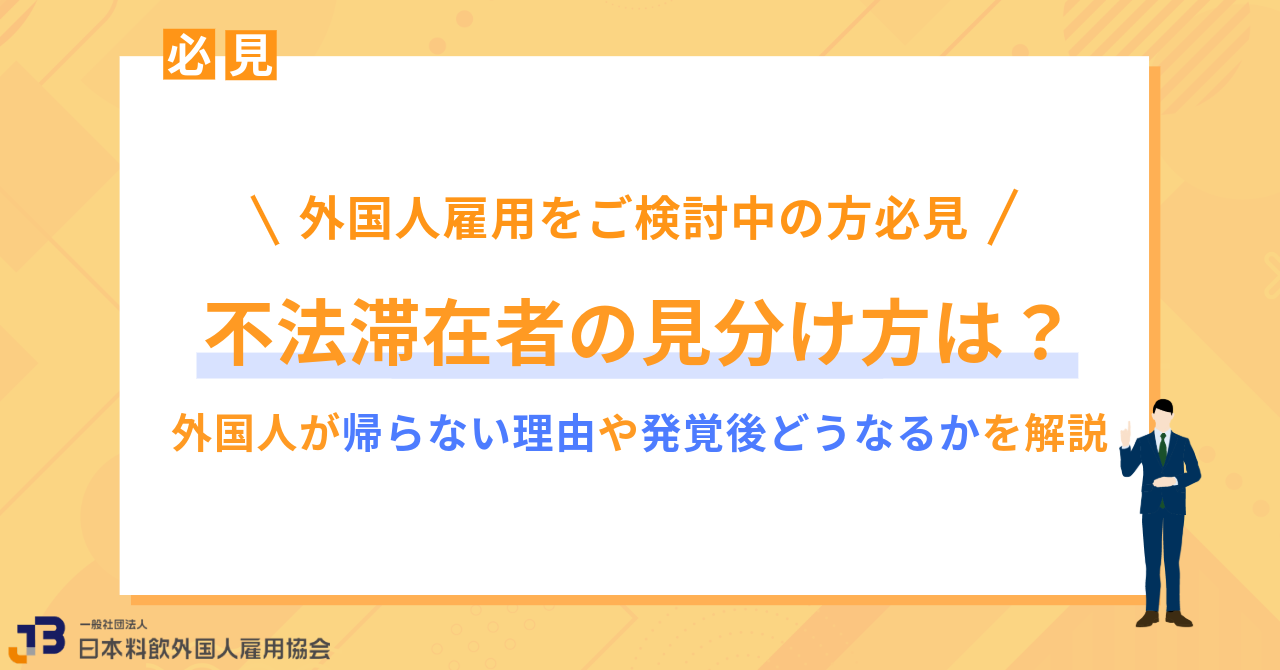「行政書士にビザ申請を依頼する際にかかる料金はいくら?」
「委託するメリットや行政書士を選ぶ際のポイントを知りたい…」
このような疑問を抱えていませんか?
行政書士にビザ申請を依頼する場合、料金は5〜20万円ほどかかります。料金に幅があるのは、対応業務の範囲や会社によって異なるためです。
そのため、行政書士にビザ申請を依頼する際は、複数社に見積もりを依頼し、サービス内容と料金を比較検討することをおすすめします。
経験豊富な行政書士に依頼すれば、ビザ申請の手間を省略でき、会社の本来の業務に集中できます。また、専門的な知識により申請の成功率向上も期待できます。
本記事では、行政書士にビザ申請を依頼する際にかかる料金を詳しく解説します。
委託するメリットや行政書士を選ぶ際のポイントについても紹介しているので、外国人の雇用を検討している企業の方はぜひ参考にしてみてください。
>>すぐに行政書士にビザ申請を依頼する際にかかる料金を知りたい方はここをタップ<<

この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
【基礎知識】行政書士とは

行政書士とは、役所などの行政に提出する書類の作成や申請手続きを代行する国家資格者です。ここでは以下2つのトピックスに分けて、行政書士についてさらに深掘りしていきます。
- 行政書士の役割と対応業務
- 入国ビザと在留資格の申請代行における違い
順番に見ていきましょう。
行政書士の役割と対応業務
行政書士は、行政書士法にもとづく国家資格者で、役所に提出する書類の作成や申請手続きをします。
外国人雇用の分野では、入国管理局への申請業務を専門的に扱っています。
ビザ申請には書類作成や入国管理局とのやり取りなど専門的な知識と経験が必要であるため、企業の人事担当者が対応するのは困難です。
 FES監修者
FES監修者行政書士に依頼すれば、外国人雇用の公的手続きの専門家として企業や外国人本人に代わり、複雑な手続きを進めてもらえます。
また、申請取次行政書士の資格を持つ行政書士であれば、申請人の代わりに入国管理局で申請書類の提出が可能です。


入国ビザと在留資格の申請代行における違い
入国ビザと在留資格は混同されがちですが、2つはまったくの別物です。
入国ビザは、外国人が日本に入国するために現地の日本領事館・大使館で取得する許可書です。
一方、在留資格は日本に住む外国人がどのような目的で滞在しているのかを示すもので、特定技能や短期滞在など29種類に分類されています。
なお、行政書士によるビザ申請は、正確には在留資格の申請を指します。


「入国ビザや在留資格の特徴についてもっと理解を深めたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
【一覧】行政書士にビザ申請を依頼する際にかかる料金


日本行政書士連合会の令和2年度報酬額統計調査の結果によると、行政書士に依頼する際にかかる料金の平均は以下のとおりです。
| 料金(平均) | |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請(就労資格) | 113,881円 |
| 在留資格変更許可申請 (就労資格) | 95,378円 |
| 在留期間更新許可申請(就労資格) | 54,447円 |
| 永住許可申請 | 131,527円 |
| 帰化許可申請(雇用者) | 177,500円 |
ここでは、行政書士にビザ申請を依頼する際にかかる料金を5つ紹介します。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 永住許可申請
- 帰化許可申請
順番に見ていきましょう。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、日本に中長期滞在する予定の外国人が上陸審査を円滑に進めるための書類です。
行政書士に在留資格認定証明書交付申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
| 料金 | 就労資格 | 非就労資格 |
|---|---|---|
| 平均 | 113,881円 | 101,557円 |
| 最小値 | 10,000円 | 5,000円 |
| 最大値 | 300,000円 | 330,000円 |
行政書士に在留資格認定証明書交付申請を依頼する際は、100,000円前後の費用を見込んでおきましょう。
なお、就労資格と非就労資格の平均では、約10,000円の差があります。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、日本に滞在している外国人が活動内容を変更したいときに必要な手続きです。
在留資格を変更せずに新しい活動を開始した場合、在留資格が取り消される可能性があります。
行政書士に在留資格変更許可申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
| 料金 | 就労資格 | 非就労資格 |
|---|---|---|
| 平均 | 95,378円 | 89,952円 |
| 最小値 | 5,000円 | 20,000円 |
| 最大値 | 330,000円 | 280,000円 |
在留資格変更許可申請にかかる費用相場は就労資格だと約95,000円、非就労資格だと約90,000円です。
在留資格認定証明書交付申請と比較すると、10,000円ほど料金が安い傾向にあります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は在留資格を維持したまま、日本に滞在できる期間を延長する手続きです。
在留期限を1日でも過ぎた場合はオーバーステイとなり、処分を受ける可能性があるため、必ず手続きを実施してください。
行政書士に在留期間更新許可申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
| 料金 | 就労資格 | 非就労資格 |
|---|---|---|
| 平均 | 54,447円 | 46,270円 |
| 最小値 | 4,000円 | 5,000円 |
| 最大値 | 320,000円 | 220,000円 |
他のビザ申請と比較すると、行政書士に依頼した際にかかる料金が一番安い傾向にあります。
なお、在留期間更新許可申請は6ヵ月以上の在留期間であった場合、満了する3ヵ月前から申請できます。



審査に時間がかかる場合もあるため、余裕をもって手続きを進めましょう。
永住許可申請
永住許可申請は「永住者」の在留資格を取得するための申請です。
申請の許可が下りると、在留活動や在留期間に制限がなくなるなどのメリットがあります。
行政書士に永住許可申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
| 料金 | 永住許可申請 |
|---|---|
| 平均 | 131,527円 |
| 最小値 | 20,000円 |
| 最大値 | 450,000円 |
行政書士に永住許可申請を依頼する際は、約130,000円かかると想定してください。
ほかの在留資格と比較すると永住許可申請の審査は厳しいため、少しでも許可される確率を上げたい方は、行政書士に依頼しましょう。
帰化許可申請
帰化許可申請は、外国籍の方が日本国籍を取得するための申請手続きです。
帰化が許可されると日本人として生活を送れます。
行政書士に帰化許可申請を依頼する場合にかかる料金の相場は以下のとおりです。
| 料金 | 雇用者 | 個人事業主および法人役員 | 簡易帰化 |
|---|---|---|---|
| 平均 | 177,500円 | 250,667円 | 172,167円 |
| 最小値 | 44,000円 | 70,000円 | 40,000円 |
| 最大値 | 500,000円 | 715,000円 | 500,000円 |
帰化許可申請は手続きが複雑で、行政書士に依頼する際にかかる料金は高い傾向にあります。


ビザ申請を行政書士に依頼する3つのメリット


ビザ申請を行政書士に依頼するメリットを3つ紹介します。
- 時間と労力が省ける
- 申請が許可される可能性が高まる
- 安心してビザ申請を進められる
順番に見ていきましょう。
時間と労力が省ける
ビザを申請するには必要書類の準備や申請書類の作成、入国管理局とのやり取りなど手間がかかります。
行政書士に依頼すれば、ほとんどの工程を任せられるため、時間と労力が省けます。
また、行政書士は公的手続きの専門家であり、難解なビザ申請もスピーディーに進めることが可能です。
専門家に委託することで時間短縮につながり、企業側は本来の業務に集中して取り組めるようになります。
申請が許可される可能性が高まる
行政書士は豊富な専門知識と実績により、ビザ申請の成功パターンを熟知しています。
外国人労働者の状況に応じて適切な申請戦略を立て、許可につながりやすい書類の作成が可能です。
とくに、許可がおりにくいビザ申請や申請内容が複雑なケースでは、行政書士への依頼をおすすめします。



入念な準備や経験により、ビザ申請の許可率の向上が期待できます。
安心してビザ申請を進められる
ビザ申請の手続きは複雑で、一つのミスで不許可になる可能性もあります。
また、申請手続きに時間がかかると、外国人労働者の入国時期に間に合わない可能性もあります。
行政書士に依頼すれば、申請手続きがスムーズに進みやすく、外国人労働者にも安心感を与えられます。
企業側と外国人労働者の双方が安心して、仕事をはじめられるようビザ申請は行政書士に依頼することをおすすめします。
ビザ申請で行政書士を選ぶときのポイント


ビザ申請で行政書士を選ぶときのポイントは以下の3つです。
- 実績があるか
- 料金体系が明確か
- コミュニケーションに違和感がないか
順番に見ていきましょう。
実績があるか
行政書士の業務分野は幅広く、その数は1万種類を超えるとも言われています。
そのため、ビザ申請の実績や外国人雇用に関する専門的知識がある行政書士に依頼する必要があります。



また、ビザの申請なら申請取次資格を持つ、申請取次行政書士に依頼しましょう。
一般の行政書士は申請手続きを代理できませんが、申請取次行政書士なら代理も可能です。
申請取次行政書士に依頼すれば、入管へ行く手間が省け、さらに時間と労力を節約できます。
料金体系が明確か
ビザ申請にかかる料金は会社ごとに異なります。
依頼する前に、料金体系を明確にすることが重要です。
なお、対応業務の範囲によって金額が変わるため、問い合わせにて料金案内している会社もあります。
少しでも料金を抑えたいなら、何社かに問い合わせて見積もりをとってみましょう。
見積もりの段階で料金体系を曖昧に説明する会社は避けてください。
コミュニケーションに違和感がないか
ビザ申請は外国人労働者の入国に関わる重要な手続きです。
信頼できる行政書士に任せる必要があります。
初回相談で対応や誠実性などを確かめ、信頼できるか総合的に判断しましょう。
また、外国人労働者とのコミュニケーションが必要な場合もあるため、多言語に対応していると安心です。
「外国人労働者ともっとコミュニケーションを取りたい!」という方に向けて、外国人従業員との円滑なコミュニケーション術の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
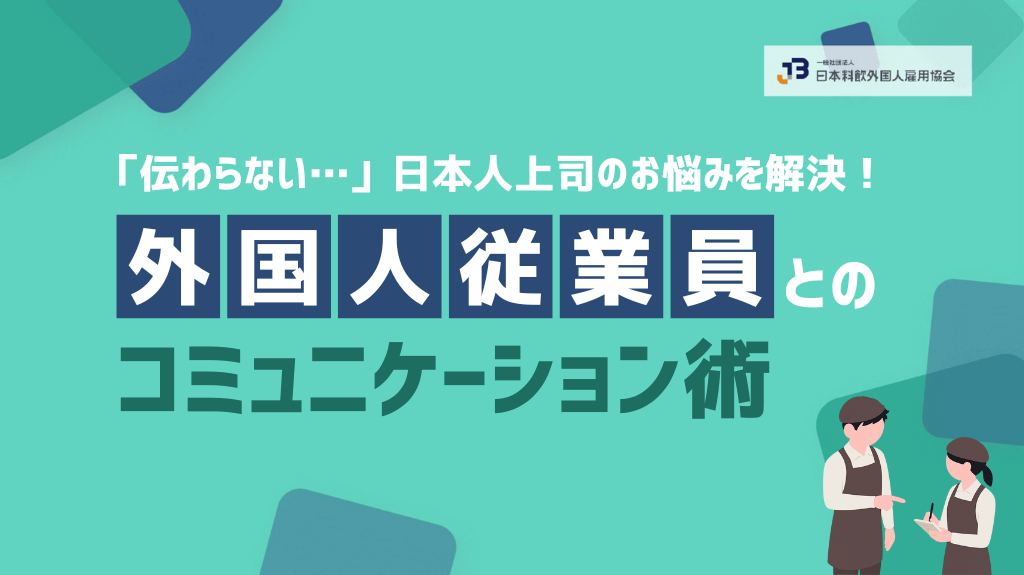
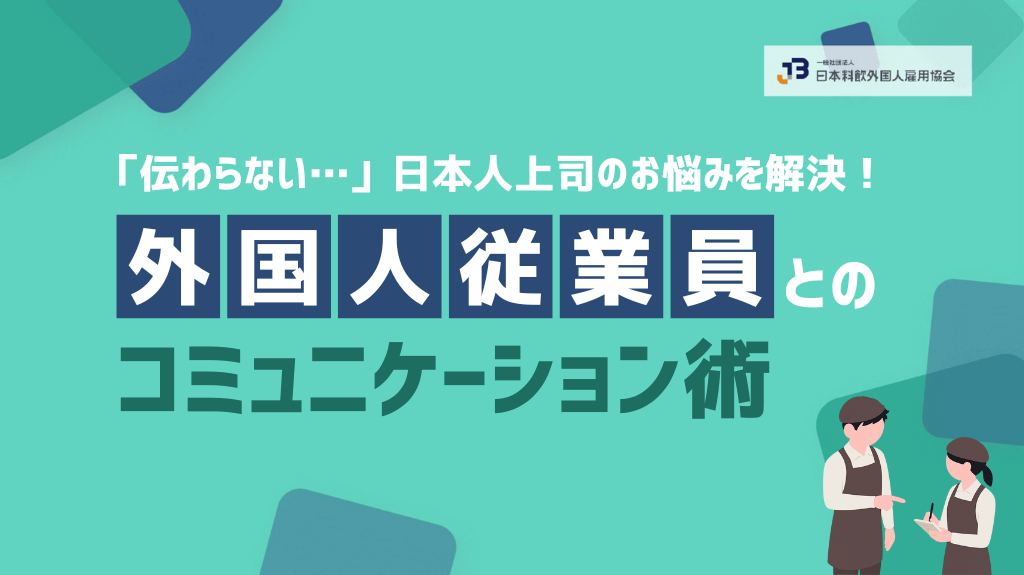
この資料でわかること
- 異文化コミュニケーションの基礎
- 文化の違いや言語の壁を乗り越えるコツ
- 効果的なコミュニケーション方法
- コミュニケーション改善の実践例 など
ビザ申請の手続きをスムーズに進めたいなら「FES行政書士法人」にご相談ください


「ビザ申請の手続きは理解できたけど、実績があり信頼できる行政書士を見つけられるか不安…」
このように感じている方も多いでしょう。
ビザの申請手続きや必要書類の作成に関するお悩みがある方は「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人の雇用に特化した行政書士法人です。豊富な実績や経験により、申請許可の取得率を高められます。
原則本人しか対応できない申請手続きも、行政書士が在籍する弊社は、本人に代わって申請の代行が可能です。
お見積もりやご相談は無料です。ビザ申請の手続きにおける必要書類の準備や作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
行政書士に依頼する際のビザ申請料金を把握して労働者の受け入れ準備を進めよう


行政書士にビザ申請を依頼する際の料金は、対応業務の範囲や会社によって大きく変化します。料金だけでなく、実績やコミュニケーションの取りやすさなどを総合的に判断することが重要です。
本記事で紹介した、委託するメリットや行政書士を選ぶ際のポイントを参考にして、ビザ申請の準備を進めてください。
とはいえ「ビザ申請の手続きを自社でうまく進める自信がない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用のサポートに特化した行政書士法人です。豊富な実績と経験を活かし、ビザ申請を円滑に進めます。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人
- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応
- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿