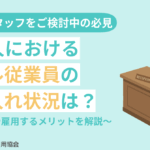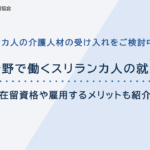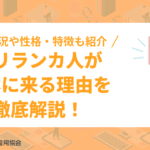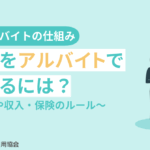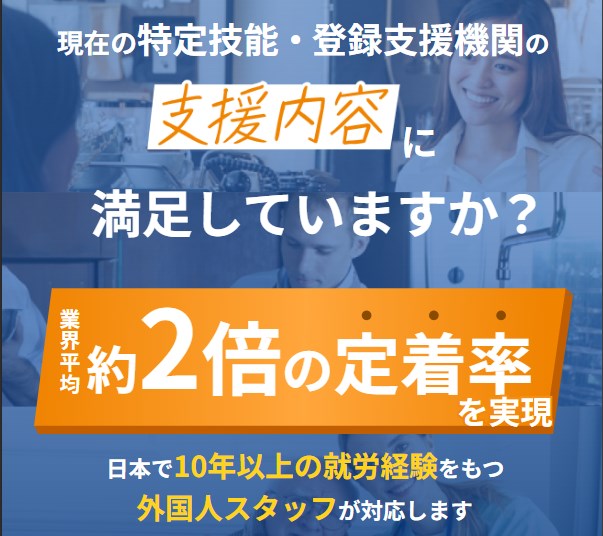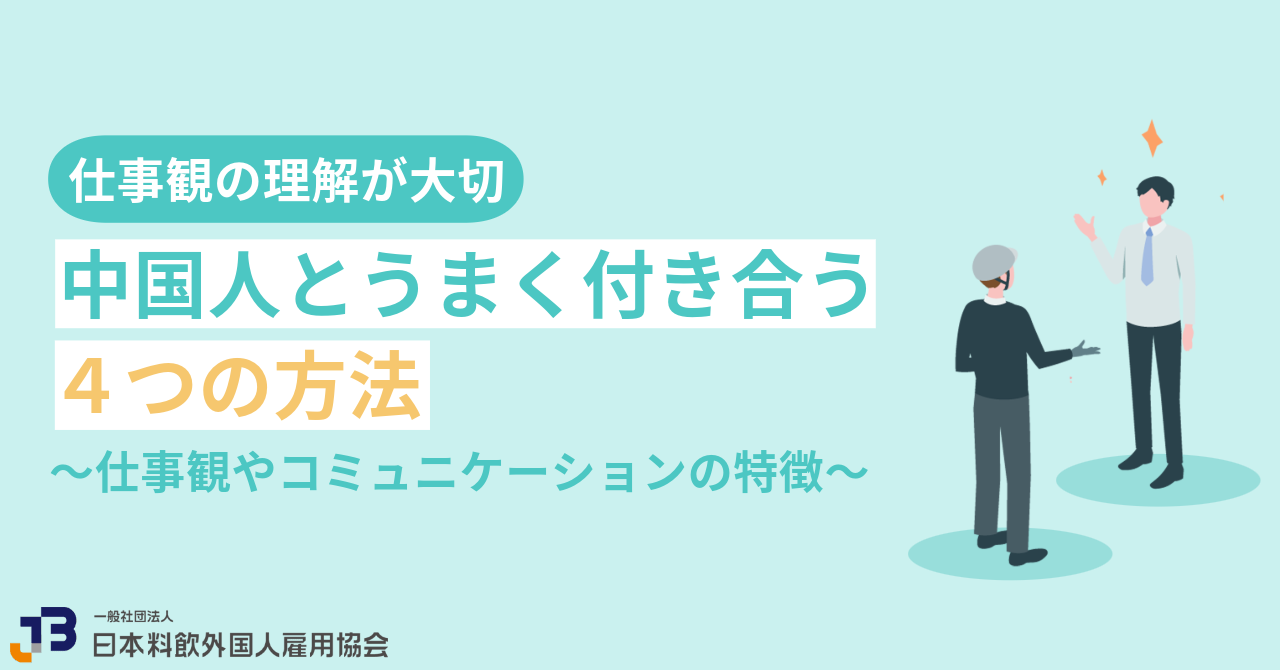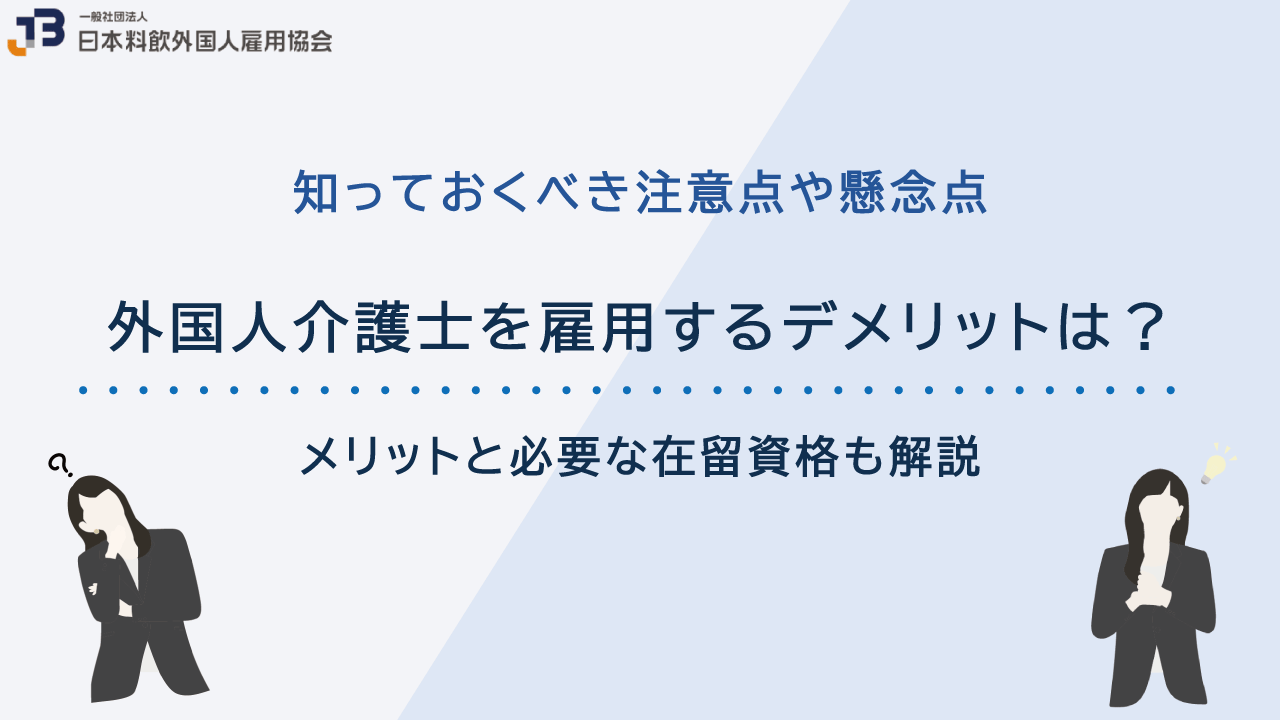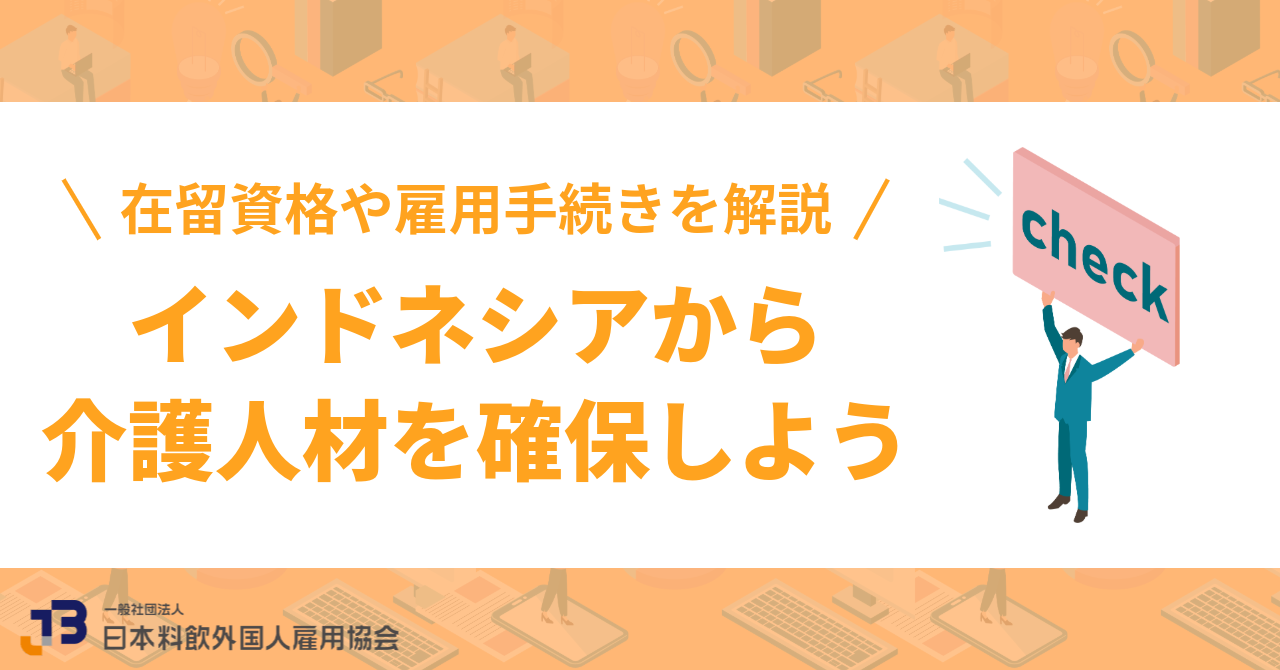「外国人を雇用したいけれど、どんな書類が必要かわからない…」
「留学生や海外在住の人を採用する際に、どこに何を提出すればいいの?」
このような疑問を抱えていませんか?
外国人を雇用する際の必要書類は、外国人本人の在留資格や現在の居住地、雇用形態によって大きく異なります。加えて、企業側も雇用契約書や採用通知書など所定の書類を準備しなければいけません。
本記事では、外国人の雇用に必要な書類や手続きの流れを条件別(留学生、海外在住者、転職者)に詳しく解説します。
雇用後に必要な届出や作成・提出時の注意点についても紹介しているので、参考にしてみてください。

この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
外国人雇用の必要書類と手続きの流れ【ケース別】

外国人を雇用する際の必要書類や手続きは、外国人の置かれている状況によって大きく異なります。
代表的なケースは、以下の3つです。
- 留学生を社員として雇用する場合
- 海外在住の外国人を雇用する場合
- 転職で外国人を雇用する場合
順番に見ていきましょう。
留学生を社員として雇用する場合
日本の大学や専門学校を卒業予定の留学生を雇用する場合、留学から就労可能な在留資格へ変更手続きをおこないます。基本的に申請は留学生本人がおこないます。
留学生を雇用する際の必要書類と手続きの流れは、以下のとおりです。
| 必要書類 | 【留学生】 ・在留カード ・パスポート ・大学の卒業証明書や卒業見込み書、または職務経歴書【企業側】 ・雇用契約書 ・採用通知書 ・直近年度の決算文書 ・前年分給与所得の法定調書合計表 など ※在留資格によって必要書類は異なります。 |
| 手続きの方法 | 出入国在留管理庁 |
| 手続きに要する期間 | 1~3ヵ月程度 |
留学生は在留資格変更許可申請をおこなうために、大学の卒業証明書や卒業見込みを証明できる書類の準備が必要です。
 猪口 裕介
猪口 裕介企業側は、雇用契約を結ぶための書類を用意しておかなくてはなりません。


海外在住の外国人を雇用する場合
海外在住の外国人を雇用する場合、在留資格認定証明書の申請が必要です。手続きに時間がかかるため、内定後は速やかに入国管理局で交付申請を進めましょう。
海外に住んでいる外国人を雇用する際の必要書類と手続きの流れは、以下のとおりです。
| 必要書類 | 【留学生】 ・パスポートのコピー ・大学の卒業証明書や卒業見込み書、または職務経歴書【企業側】 ・雇用契約書 ・採用通知書 など ・日本での活動資料 ※技術・人文知識・国際業務の場合 |
| 手続きの方法 | 1.在留資格証明書を申請する 2.発行後海外にいる採用予定者へ送付する 3.採用予定者が現地の日本大使館で就労ビザを申請する |
| 手続きに要する期間 | 1~3ヵ月程度 |
在留資格認定証をオンラインで申請した場合、証明書を電子メールで受け取り外国人に転送できるため、郵送する手間を省けます。



在留資格認定証の有効期限は3ヵ月しかないので、無効になる前に現地の大使館でビザの申請をするよう指導が必要です。
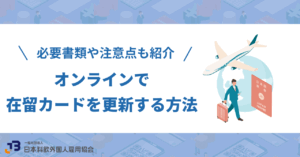
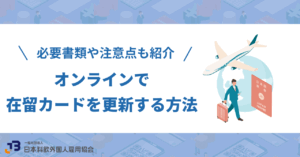
転職で外国人を雇用する場合
すでに日本で働いている外国人を雇用する場合、在留資格の確認が必須です。
もし、在留資格で認められていない活動をさせてしまうと、採用側の会社が不法就労助長罪などに問われるリスクがあるためです。
すでに日本で働いている外国人の場合の必要書類と手続きの流れは、以下のとおりです。
| 必要書類 | 【前職と同じ場合】 就労資格を確認の上、管轄の出入国管理局へ中長期在留者の受入れに関する届出書を提出する 【前職と異なる場合】 在留資格変更許可申請をする |
| 手続きの方法 | 退職前に就労資格証明書を交付してもらう(任意) |
| 手続きに要する期間 | 2週間~1ヵ月程度 |
もし現在の資格で雇用予定の業務ができない場合は、在留資格変更手続きが必要です。


「外国人を雇用する際の手順を詳しく知りたい」という方に向けて、外国人雇用スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人採用の意義
- 外国人雇用のメリット
- 外国人採用スタートの5ステップ
- よくある課題と解決策
外国人を雇用したあとに提出する必要書類


外国人を雇用した後に、外国人を受け入れたことの届出や社会保険の加入手続きが必要になります。ハローワークや出入国在留管理庁へ行き書類を提出しましょう。
雇用後の届出は、以下の4つです。
- 外国人雇用状況届出書
- 税金の手続きや保険に加入するための申請書類
- 中長期在留者の受入れの届出
各届出や申請について、項目ごとに詳しく説明します。
外国人雇用状況届出書
外国人従業員を雇用した際、企業はハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を届け出る義務があります。ただし、例外として在留資格が外交ビザまたは公用、特別永住者は報告不要です。
外国人雇用状況届は、従業員が雇用保険に加入する翌月10日前までに、加入しない場合は翌月末までに管轄のハローワークへ提出します。
外国人雇用状況届出書の記載内容は、以下のとおりです。
- 氏名
- 在留資格の種類と在留期間
- 生年月日・性別
- 在留カードの番号
- 事業所の名称、所在地など
出典:厚生労働省|外国人雇用状況届出書(様式第3号)
報告を怠ったり虚偽の内容を届け出ると、30万円以下の罰金が科される場合があります。



必ず期日までに対応し、ハローワークへ行くのが難しい方は電子申請の利用も検討してみてください。


税金の手続きや保険に加入するための申請書類
健康保険や厚生年金保険の適用事業所に常時使用される方は、社会保険の被保険者となります。ここでいう「常時使用される方」とは、一般的に正社員や、週の所定労働時間および月間の所定労働日数が正社員の4分の3以上である方を指します。
国籍や性別は関係ありませんが、この働き方の条件を満たすことが加入の主な基準です。必要書類と手続きの流れは、以下のとおりです。
| 必要書類 | ・被保険者資格取得届 ・被保険者ローマ字氏名届 ・本人確認書類のコピー |
| 手続きの方法 | 被保険者資格取得届を日本年金機構へ提出する |
介護保険は40歳以上の健康保険加入者、労災保険は全従業員が加入対象です。雇用保険は週20時間以上勤務し31日以上雇用見込みがある場合、加入義務があります。



手続きを怠ると罰則が科される可能性があるため、入社後速やかに手続きを進めましょう。
中長期在留者の受入れの届出
中長期在留者と呼ばれる3ヵ月以上滞在予定の外国人を雇用する場合、出入国在留管理庁への届出が義務付けられています。届出は雇用開始から14日以内におこなう必要があります。
以下の届出事項を記載し、所属機関の職員が提出します。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍
- 地域
- 住居地及び在留カード番号の共通記載事項
- その他状況に合わせた届出事項
出典:出入国在留管理庁|中長期在留者の受入れに関する届出
中長期在留者の届出はハローワークへ提出する雇用状況届出とは別の手続きなので、地方出入国在留管理局への届出を忘れず済ませましょう。持参または郵送以外に、インターネットで登録も可能です。
外国人雇用で必要書類を作成・提出する際の注意点
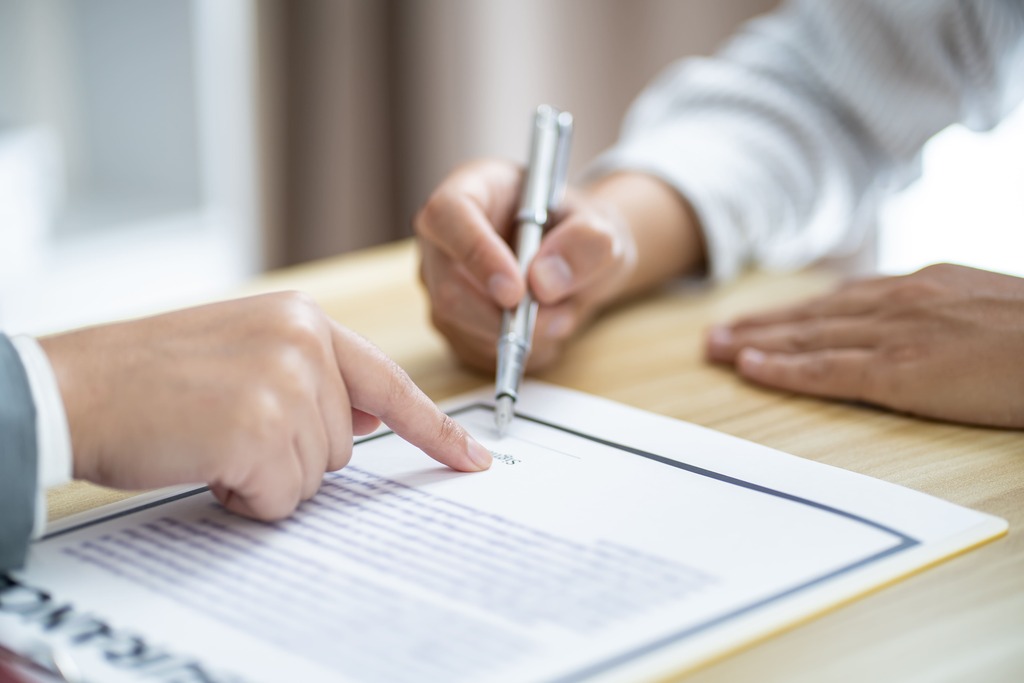
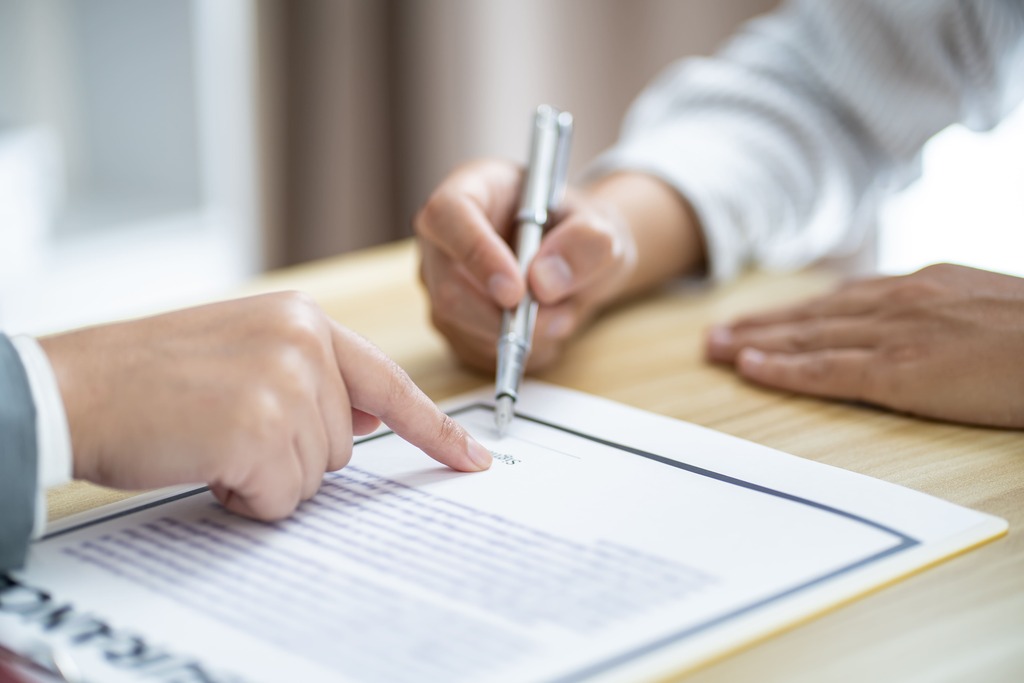
外国人雇用に関する必要書類を作成・提出する際は、さまざまな注意点があります。とくに外国人材の在留資格に関わる手続きは、正確さ、期日厳守が非常に重要です。
主な注意点は以下の3つです。
- 申請がとおる要件を把握しておく
- 外国人が理解できる言語で作成する
- 提出期限を過ぎないようにする
書類に不備があると、審査に時間がかかり申請が間に合わない可能性があります。何に注意しなければいけないのか、詳しく解説していきます。
申請がとおる要件を把握しておく
外国人材を雇用する際は、日本人採用にはない特有の手続きや関連法規を遵守する必要があります。ルールを守らないと、罰則を科されるリスクがあります。
また、要件を把握し書類を作成しなければ、申請が通らず予定通り雇用できない可能性もあるため注意してください。
申請時に重要なのは、以下の2つです。
- 雇用する業務内容が在留資格の活動範囲と合っているか
- 在留資格が有効期限切れではないか
ほかにもハローワークへの届出義務など、怠ると罰金となる手続きもあります。要件が複雑で不安な場合や、申請をスムーズに進めたい場合は、行政書士などの専門家に相談または依頼するのも有効な手段です。


外国人が理解できる言語で作成する
書類を外国語で記載しなければいけないという決まりはないものの、外国人従業員との間で契約内容や労働条件に関する言葉の壁による誤解が、後々のトラブルに繋がるケースは少なくありません。トラブルを防ぐためにも、本人が理解できる言語で正確に伝えることが重要です。
また、特定技能1号外国人の義務的支援の中に、相談や苦情などは外国人が十分理解できる言語で対応すると定められています。
外国人材が理解できる言語への翻訳や説明、生活上のサポートといった支援業務は、登録支援機関に業務委託することで専門的に対応してもらえます。
登録支援機関とは、出入国在留管理庁から認定を受けた、特定技能外国人の支援を専門に行う機関です。専門の方に任せれば、自社の業務に専念できるメリットがあります。
どの登録支援機関に委託すれば良いのか迷ったら「日本料飲外国人雇用協会」がおすすめです。
日本料飲外国人雇用協会は、外食、飲食料品製造、介護分野における外国人の就労支援に強みを持つ登録支援機関です。行政書士法人と連携しているため、在留資格の申請や更新などの法的手続きもスムーズに進められます。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
提出期限を過ぎないようにする
必要書類の提出期限が過ぎてしまうと、申請許可が降りずに、予定どおりに雇用を開始できなくなります。
また、在留資格の更新や変更を忘れると、在留期間を超過してオーバーステイとなってしまいます。
オーバーステイが発覚すれば、外国人本人が退去強制処分の対象です。在留資格を確認せず受け入れた企業側も「不法就労助長罪」に該当し、事業主も処罰を受ける可能性もあります。
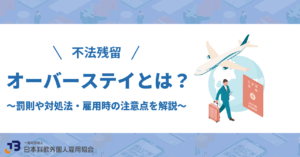
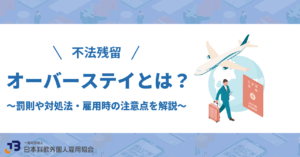
「外国人雇用の法律に関する理解をさらに深めたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
外国人雇用の必要書類における用意や作成にお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください


「外国人雇用の必要書類は理解できたけど、不備なく提出や申請ができるか不安」
このように感じている方も多いでしょう。
外国人雇用の必要書類や作成に関するお悩みがある方は「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用の申請や在留資格の変更・更新における公的手続きの支援を専門とする行政書士法人です。原則本人しか対応できない申請手続きも、行政書士が在籍する弊社は、本人に代わって申請の代行が可能です。
弊社は、外国人就労者に特化した事業を展開しているため、豊富なノウハウと知見で、外国人雇用の申請手続きをスムーズかつ確実に進めます。
無料相談を受け付けていますので、外国人雇用における必要書類の準備や作成にお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
外国人雇用の必要書類を把握して採用の準備を進めよう


外国人を雇用する場合、企業側だけでなく、外国人本人にも必要書類を準備してもらわなくてはなりません。必要書類が不足していたり、記入ミスがあったりすれば、手続きがスムーズに進まず、外国人の雇用が遅れてしまいます。
本記事で紹介した、必要書類と手続き方法を参考に、計画的かつ正確な申請準備を進めてみてください。
とはいえ「外国人雇用の必要書類、自社で準備して作成できるかわからない」と不安を持つ方もいるでしょう。 このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人雇用の就労支援を専門とする行政書士法人です。専門分野での豊富な実績と専門的な知識で、企業様の外国人採用をトータルにサポートいたします。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人
- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応
- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿