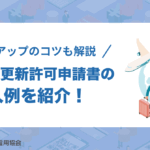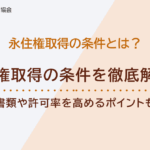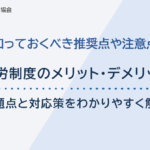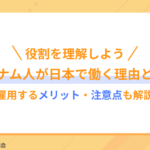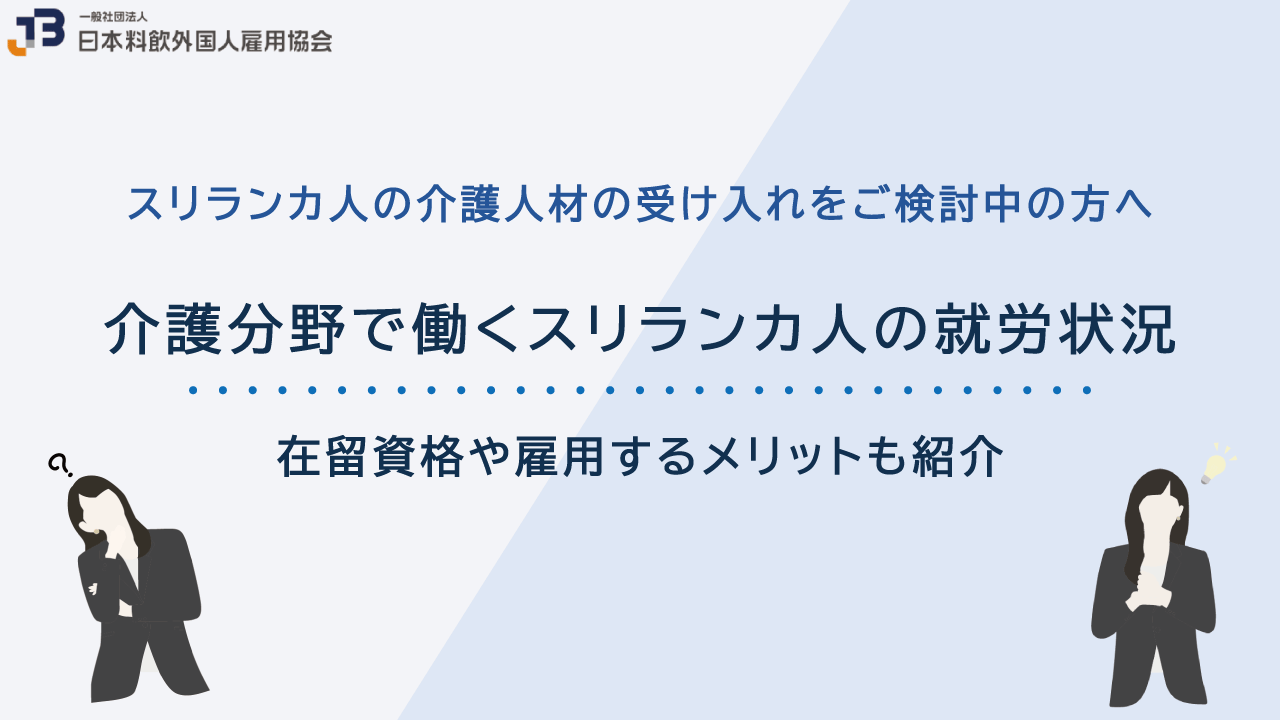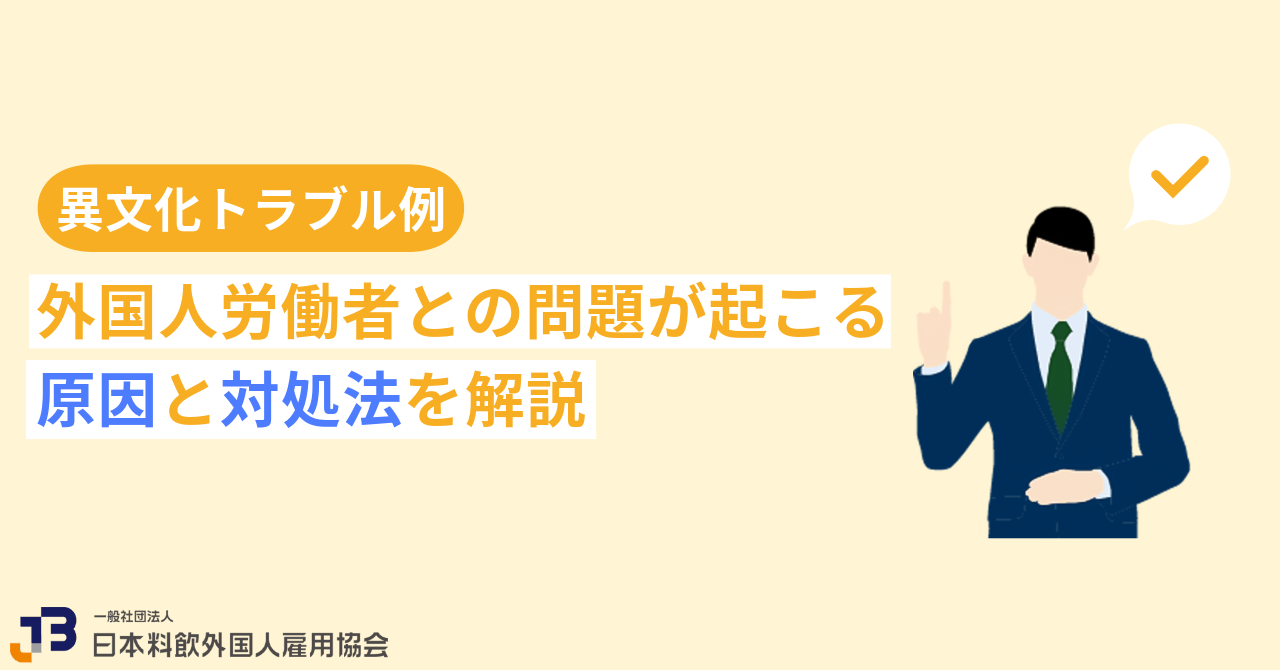「申請取次行政書士ってなに?」
「どんな依頼ができるの?」
このような疑問をお持ちではないでしょうか?
申請取次行政書士とは、外国人のビザや在留資格の申請手続きを代理でおこなえる行政書士のことです。一般の行政書士が「申請取次研修」を受講し、研修を修了すれば申請取次行政書士になれます。
一般の行政書士は、申請書類の作成は代理できるものの、申請手続きを代理ではおこなえません。この差が、一般の行政書士と申請取次行政書士の大きな違いです。
外国人雇用を導入する場合、ビザや在留資格の申請手続きが必要なことがほとんどです。いざというときのために、相談者の一人として申請取次行政書士の存在を覚えておきましょう。
本記事では、申請取次行政書士について詳しく解説します。頼める業務内容や依頼するメリットも紹介しているので、記事を読んで理解を深めましょう。

この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
申請取次行政書士とは?【3つのトピックスで詳しく解説】
申請取次行政書士とは、外国人のビザや在留資格の申請手続きを代理におこなう行政書士のことです。以下の3つのトピックスに分けて、申請取次行政書士についてさらに深掘りしていきます。
- 行政書士の申請取次制度により誕生した専門家
- 申請取次行政書士ができること
- 申請取次行政書士になる方法
順番に見ていきましょう。
もし「ビザ」と「在留資格」の違いがあいまいな方は、下記の記事で詳しく紹介しているのでご一読ください。

申請取次行政書士は「申請取次制度」により誕生した専門家
申請取次行政書士は「申請取次制度」により誕生した専門家です。
制度が導入される前は、ビザや在留資格の申請手続きがおこなえるのは原則本人だけでした。しかし、申請者増加による窓口の混雑や手続き方法を知らない本人の負担が課題となっていました。
 FES監修者
FES監修者そこで採択されたものが「申請取次制度」です。
制度内で申請取次行政書士というポジションを創設し、本人に代わって申請手続きができる環境を整えました。以下は、一般の行政書士と申請取次行政書士が対応できる業務内容を比較した表です。
| 業務内容 | 行政書士 | 申請取次行政書士 |
|---|---|---|
| ビザ・在留資格の書類の作成代理 | 可 | 可 |
| ビザ・在留資格の申請手続きの代理 | 不可 | 可 |
申請手続きまで代理できる申請取次行政書士の誕生により、窓口担当者や外国人の負担は大きく軽減しました。
なお、2025年に「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、行政書士の使命の明確化やデジタル社会の進展を踏まえた国民の利便の向上および業務の改善進歩、特定行政書士の業務範囲の拡大などの変更があり、令和8年1月1日から施行されます。
法改正による影響として、取次申請行政書士の業務や手続き方法についてはまだ詳細が明確になっていません。しかし、今後のサービス向上や業務効率化が期待されると考えられます。
参考:衆議院|行政書士法の一部を改正する法律の公布について
申請取次行政書士ができること
くりかえしですが、申請取次行政書士の主な仕事は、ビザや在留資格の申請手続きの代理です。具体的には、以下の手続きに携われます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 再入国許可申請
- 在留カードの有効期間更新申請
- 在留カードの住居地以外の記載事項変更届出
- 在留カードの再交付申請
- 在留カードの受領
出典:法務省|申請等取次制度の概要
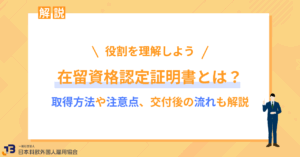
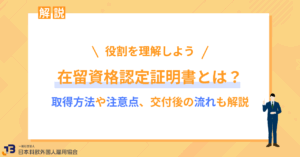
申請取次行政書士は、外国人の入国管理に関するあらゆる手続きの代理を担えます。
「在留資格の特徴や変更手続きについて理解を深めたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
申請取次行政書士になる方法
申請取次行政書士として活動するためには、以下7つの手順を踏む必要があります。
- 行政書士の試験に合格する
- 日本行政書士会に登録する(弁護士や税理士も登録可)
- 国が管轄する研修会を受講する
- 設問式の効果測定を受ける
- レポート課題を提出する
- ④⑤合格後、研修会の修了証書が交付される
- 単位会を通じて地方出入国在留管理局に届け出る
修了証書の提出を含む必要手続きが完了すれば、申請取次行政書士として活動できます。
事業主が申請取次行政書士に手続きを依頼する5つのメリット
外国人労働者を雇用する場合、事業主が申請取次行政書士に手続きを依頼するメリットは主に以下の5つです。
- 手続きの時間と労力が省ける
- 申請がスムーズに進む
- 法令を守り適切な手続きがおこなえる
- 申請許可の取得率が高まる
- 外国人労働者に安心感を与えられる
依頼を検討する判断材料に役立ててください。
1.手続きの時間と労力が省ける
外国人のビザや在留資格の申請には、以下のような手続きが伴います。
- 必要書類を揃える
- 申請書類を作成する
- 外国人とメールや電話でやりとりをする
- 地方出入国在留管理局に必要書類を届け出る
手続きを外部に依頼すれば、これらの手続きにかかる時間と労力を削減できます。



事業主側は、不慣れな手続きに翻弄されることなく、仕事に専念できるでしょう。
2.申請がスムーズに進む
専門知識をもった申請取次行政書士が手続きをおこなうと、申請がスムーズに進みます。
- 申請に必要な書類を把握している
- 手続きの流れや注意点を知っている
- 申請担当者の指示が的確に理解できる
自身で申請を実施するのは不可能ではありません。しかし、申請に関する知識が不足しがちで、どうしても非効率になってしまいます。
その点、専門家である申請取次行政書士は外国人のビザや在留資格に関するプロです。プロに任せた方が、申請の進行が確実に早いのは明らかです。
3.法令を守り適切な手続きがおこなえる
申請取次行政書士に依頼すると、法令を遵守した適切な手続きをおこなってくれます。
ビザや在留資格の申請は「出入国管理及び難民認定法」が定める規定に基づき審査されています。万が一、虚偽の報告や不適切な手続きをおこなえば、申請許可が下りないだけでなく、違反となり処罰の対象となります。



安全に外国人雇用を図りたいなら、法的知識に詳しい申請取次行政書士に依頼するのがおすすめです。
「外国人雇用のための手続きを自社でも把握しておきたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人雇用時の関連法令の基本
- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例
- 労働条件と雇用契約
- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など
4.申請許可の取得率が高まる
申請許可は「出入国管理及び難民認定法」が定める要件を満たした者に与えられます。しかし、具体的な審査基準は公表されていません。
申請取次行政書士は、専門知識とこれまでの実績から、取得に成功する傾向を把握しています。



自社が手探りで進めるよりも、取得率が高いでしょう。
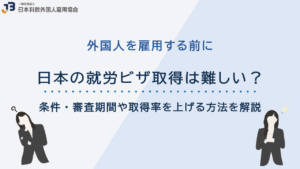
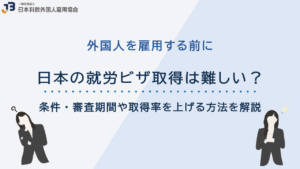
5.外国人労働者に安心感を与えられる
申請取次行政書士への依頼は、外国人労働者の安心感につながります。申請手続きがスムーズに進むと、不安や焦りが生まれません。指示や説明も的確なため、不満も生まれにくくなります。
採用段階で安心感を与えられることで、早期退職のリスク軽減にもつながります。今後長く働いてもらえる人材確保のためにも、申請取次行政書士に依頼し信頼できる環境を作ることが重要です。
申請取次行政書士がいる事業所を選ぶときのポイント


申請取次行政書士がいる事業所を選ぶときのポイントを3つ紹介します。
- 幅広い在留資格に対応できる事務所を選ぶ
- 外国人材の雇用後にもサポートがある事務所を選ぶ
- 対応が丁寧な事務所を選ぶ
順番に見ていきましょう。
幅広い在留資格に対応できる事務所を選ぶ
在留資格は全部で29種類あり、職種や業務内容によって適用される資格が異なります。
優秀な外国人労働者を逃さないためには、幅広い在留資格に対応できる事務所を選ぶことが重要です。



とくに自社の事業とマッチする在留資格に対応している事務所か必ず確認しましょう。
幅広い在留資格に対応できる事務所であれば、採用を検討できる外国人が増えるため、優秀な人材を見つけられる可能性が高まります。
外国人材の雇用後にもサポートがある事務所を選ぶ
申請取次行政書士がいる事務所を選ぶ際は、外国人労働者の雇用後にもサポートがあるか確認してください。
外国人労働者の雇用は、採用時の手続きで終わりではありません。
企業は外国人労働者に対して、在留期間更新や在留資格変更など雇用後にもさまざまなサポートが求められます。
また、雇用後もサポートがある事務所を選ぶことで、外国人労働者の雇用を長期的に安定させられます。
対応が丁寧な事務所を選ぶ
外国人雇用に関する申請手続きは、知識がない人にとっては理解が難しいです。
そのため、説明がわかりやすく対応が丁寧な事務所を選ぶことをおすすめします。
行政書士は、大切な外国人従業員の申請手続きを任せる重要なパートナーです。



連絡の速さや対応の丁寧さなどから、信頼できる事務所か見極めてください。
なお、多くの行政書士事務所が無料相談を実施しています。
実際に相談し、外国人従業員の申請手続きを任せるに値する事務所であるか確認しましょう。
申請取次行政書士に手続きを依頼するなら「FES行政書士法人」にご相談ください
「自社で外国人労働者の申請手続きを進めるより専門家に依頼したほうが良さそう…」
このように感じている方も多いでしょう。
外国人のビザや在留資格の申請手続きを申請取次行政書士に依頼したい場合は「FES行政書士法人」にご相談ください。弊社は外国人雇用に関する必要書類の準備や申請手続きを専門とする行政書士法人です。
申請取次行政書士が在籍しているため、原則本人しか対応できない申請手続きも代理できます。また、専門知識とこれまでの経験を活かし、ビザや在留資格を取得できる確率を高めます。
無料相談を受け付けているので、外国人のビザや在留資格の申請手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
申請取次行政書士に関するよくある質問
申請取次行政書士に関するよくある質問と回答をまとめました。
申請取次行政書士になるのは難しい?
行政書士の試験で学んだ知識と現場での経験があれば、申請取次行政書士の研修で修了認定をもらうのはそこまで難しくありません。
ただし、研修後の効果測定と課題レポートの結果が悪いと、修了証書を交付してもらえません。
一発で申請取次行政書士になるためにも、集中して研修に参加しましょう。
申請取次行政書士になるための研修費用はいくら?
申請取次行政書士になるための研修費用は約3万円です。
これは日本行政書士会連合会が開催している「申請取次研修」の受講料で、VOD方式で受講できます。
受講機会は限られているため、申請取次行政書士になりたい方は早めに申し込みましょう。
申請取次行政書士は更新が必要ですか?
申請取次行政書士の有効期間は3年のため、更新手続きが必要です。
更新希望の方は、必要な書類を揃えて郵送または出入国在留管理庁の窓口にて有効期限内に手続きを済ませましょう。
参考記事:出入国在留管理庁|更新手続について
申請取次行政書士の役割を知って外国人雇用の手続き依頼を検討しよう
申請取次行政書士は、外国人のビザや在留資格の申請手続きを代理できる行政書士です。
事業主が申請取次行政書士に手続きを依頼すれば、時間と労力を削減でき、申請許可の取得率を高められます。
本記事で紹介した申請取次行政書士に手続きを依頼するメリットや事業所を選ぶときのポイントを参考にして、外国人労働者の申請準備を進めてください。
とはいえ「行政書士法人事務所がたくさんあって、どの事務所に依頼すれば良いかわからない…」という方もいるでしょう。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。
弊社は、外国人労働者の申請手続きを専門とする行政書士法人です。豊富な実績と専門知識で、企業様の外国人採用をサポートいたします。
無料相談を受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。


- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人
- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応
- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿