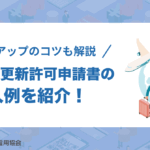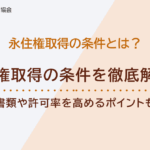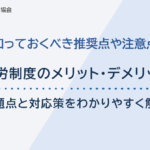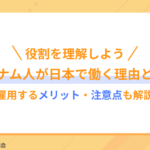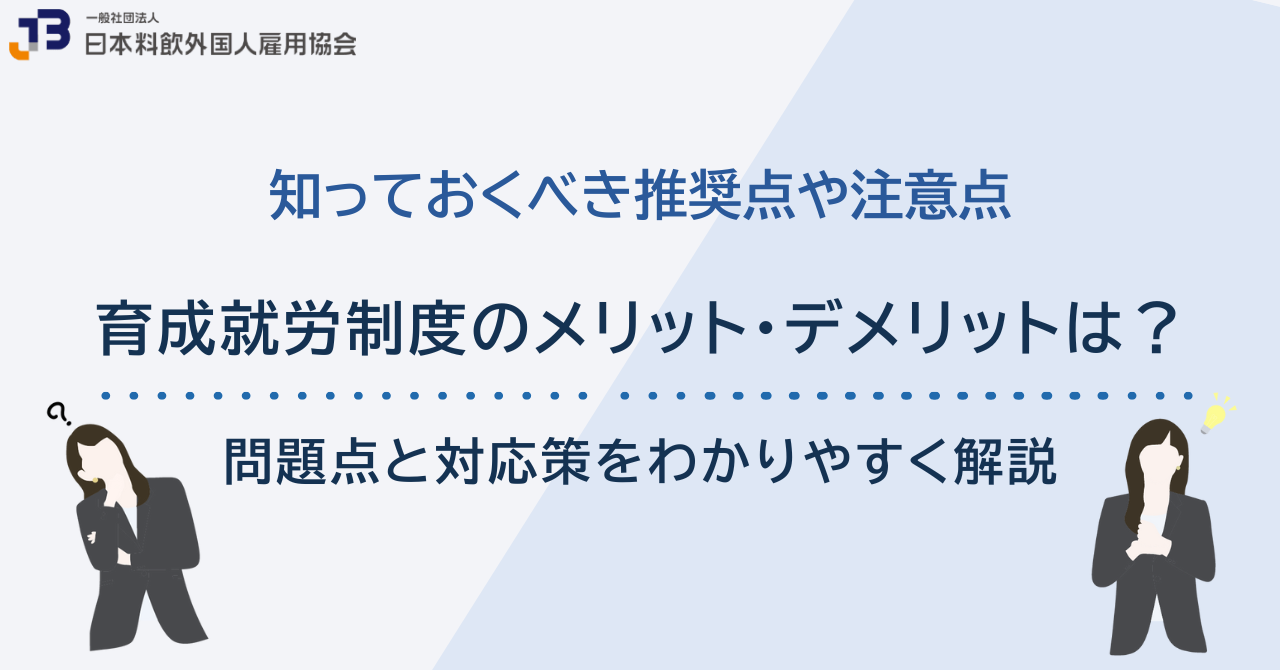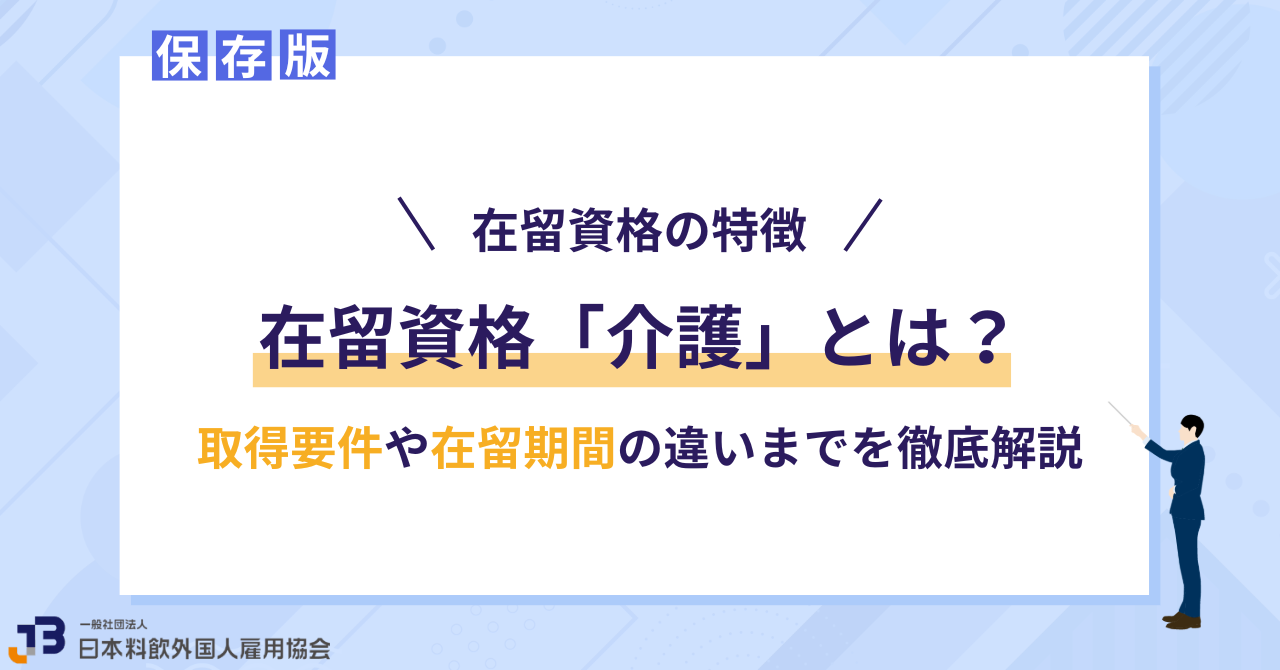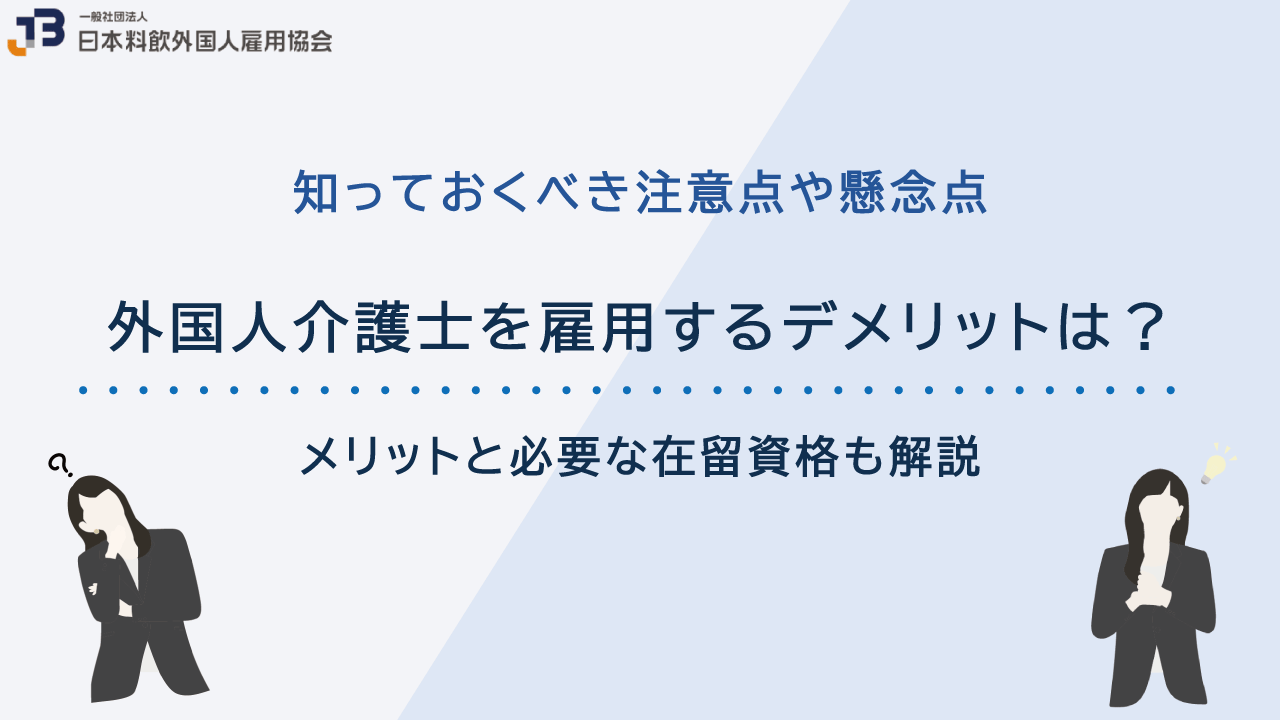※2025年9月までの発表資料を元に作成
「育成就労制度の利用を検討中だからメリット・デメリットを知りたい」
「もし問題点があるなら対応策も教えてほしい」
このような悩みをお持ちの方も多いでしょう。
育成就労制度は、長期的な外国人材の受け入れを目的とした制度です。技能実習制度の後継として2024年に新たに創設されました。
育成就労制度は、人手不足の解消や長期雇用を見据えた人材確保といったメリットがある一方、雇用にかかる費用負担の拡大や受け入れ可能な職種の減少といったデメリットがあります。
制度の良い面を最大限に活かしたい方は、デメリットに対する対応策を事前に考えておきましょう。
本記事では、育成就労制度のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。制度の問題点における対応策も紹介しているので、記事を参考に制度の導入準備を進めてみてください。

この資料でわかること
- 外国人採用の意義
- 外国人雇用のメリット
- 外国人採用スタートの5ステップ
- よくある課題と解決策
育成就労制度とは【わかりやすく解説】

育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的とする制度です。技能実習制度を見直した新たな制度として注目されています。
技能実習制度は、国際貢献を目的に、発展途上国等の外国人に日本の技術や知識を教えるための制度です。廃止が決まった主な理由は、技能実習生を不当に働かせる企業が増え、本来の制度の目的と実際の運用にズレが生じたためです。
現在、技能実習は廃止に向けた移行期間の段階で、2027年に育成就労制度での受け入れが開始される予定となっています。※2025年9月までの発表資料を元に作成
以下の記事では、育成就労制度について徹底解説しています。詳細を知りたい方はあわせてご覧ください。
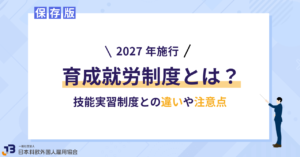
育成就労制度の4つのメリット

育成就労制度の利用は、企業側と外国人材の両方にメリットがあります。
主なメリットは以下の4つです。
- 人材を柔軟に配置できる
- 技能実習生と比べ日本語能力が高い人材を確保できる
- 育成就労外国人の経済的負担が減る
- 育成就労外国人の転籍が可能になる
順番に見ていきましょう。
1.人材を柔軟に配置できる
人材を柔軟に配置できる点も育成就労制度を利用する企業側のメリットです。
技能実習制度は、技術の習得を目的としているため、レジ打ちや清掃などの単純労働は認められません。
しかし、育成就労制度は、労働力としての人材確保が許可されており、特定技能制度と同様の業務に従事することが可能になります。
 猪口 裕介
猪口 裕介柔軟に外国人材を配置できる仕組みは、人手不足に悩む企業にとって助かるポイントです。
以下の記事では、技能実習と特定技能の違いを詳しく解説しています。制度の違いの理解を深めたい方はあわせてご覧ください。


2.技能実習生と比べ日本語能力が高い人材を確保できる
育成就労制度で、特定技能の在留資格を取得する外国人には、一定の日本語能力が求められます。
具体的には就労を開始するまでに、日本語能力A1(数字が低いほど難易度が低い)相当以上の試験(日本語能力試験のN5等)に合格または、それに相当する日本語の講習の受講を済ましておく必要があります。
技能実習制度では、外国人に対してN4程度の日本語能力が推奨されているものの、必須ではありません。※一部日本語能力の指定がある職種あり
最初から一定の日本語能力を持つ外国人を雇用できると、企業には以下のようなメリットがあります。
- 日本語教育の手間を省ける
- 指示が伝わりやすく教育コストを削減できる
- コミュニケーションを取りやすく生産性アップが期待できる
日本語能力の基準が設けられることで、企業は即戦力となる人材を採用しやすくなります。
3.育成就労外国人の経済的負担が減る
育成就労外国人側のメリットとしては、経済的負担が減る点です。
技能実習制度を活用して日本で働く実習生は、「送り出し機関」と呼ばれる専門の仲介業者への派遣手数料は自己負担のため、借金する方も多いです。
出入国在留管理庁が実習生の借金額を調査したところ、借金の平均値は54万7,788円でした。※送り出し機関以外への出費も含む
育成就労制度では、これまで負担していた費用を企業側と育成就労外国人で負担します。育成就労外国人は経済的負担が軽減され、借金による不安やストレスから解放されます。
4.育成就労外国人の転籍が可能になる
技能実習制度は、本人意向の転籍は原則認められていません。※やむを得ない事情を除く
そのため、過酷な労働環境を強いられたり、不当な扱いを受けたりする状況で我慢して働く外国人も多いです。
育成就労制度では、同じ分野の職種内であれば、就労期間や技能・日本語レベルの要件はあるものの転籍が可能です。
自分が納得できる労働条件や働きやすい環境を求めて転職できるため、外国人労働者の人権が守られやすくなります。
育成就労制度の3つのデメリット・問題点


次は、育成就労制度のデメリットに触れていきます。
主なデメリットは以下の3つです。
- 企業側の経済的負担が増える
- 受け入れ可能な職種が狭まる
- 転職されやすい
制度の問題点がわかれば、後述する対応策を活用して適切に対処できます。
1.企業側の経済的負担が増える
育成就労制度では、これまで実習生が支払っていた各種関連費用を企業側が負担することになります。
以下は企業側の負担が求められる費用です。
- 渡航関連の費用(宿泊費・航空運賃)
- 送り出し機関への費用(仲介手数料・研修実施費)
- 教育関連の費用(日本語教育費・教材費)
育成就労外国人の出身地や企業の支援範囲にもよりますが、外国人材一人あたりにかかる負担は、50〜100万ほどかかるとされています。



受け入れを検討する場合、企業側は資金を事前に確保しておきましょう。
2.受け入れ可能な職種が狭まる
育成就労制度は、特定技能制度と同様の業務が認められるため利便性が向上したものの、受け入れ可能な職種は狭まります。
技能実習制度では、令和7年3月時点で、91職種168作業への従事が認められています。
一方で、育成就労制度は特定技能1号への移行を前提とするため、従事できるのは特定技能制度と同様に16分野の見込みです。※2025年9月までの発表資料を元に作成
企業側は自社の業務が対象に含まれない場合、育成就労制度を利用して外国人を雇用できません。
3.転職されやすい
本人の意向で自由に転籍が可能になる育成就労制度では、企業側にとって転職されやすいデメリットにつながります。
長期雇用を見据えた人材を確保したいと思っても、転職の決定権は外国人材にあるため安定性は確保できません。
長く勤めてもらいたいなら、外国人が安心して働ける環境を整えていく必要があります。
育成就労制度のデメリットを解決する対応策


先ほど挙げたデメリットや問題点には、解消を図る対応策があります。
- 国の助成金を積極的に活用する
- 働きやすい職場環境を整える
詳しく解説するので、導入準備を進める際の参考にしてみてください。
国の助成金を積極的に活用する
企業側の経済的負担は、国の助成金を積極的に活用することによりカバーできます。
以下は外国人労働者を受け入れる企業が活用できる助成金の一例です。
| 助成金の種類 | 助成金の内容 |
|---|---|
| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 外国人特有の事情に配慮した就労環境を整備する際にかかる費用を一部助成するもの |
| 雇用調整助成金 | 経営上の理由で事業の縮小を余儀なくされた事業主に対し、従業員の雇用維持にかかる費用を助成するもの |
| 人材開発支援助成金 | 労働者が知識および技術を習得する際にかかる訓練費や準備費の一部を助成するもの |
送り出し機関に支払う手数料や航空運賃などを直接補償してくれるわけではありません。しかし、助成金を上手く活用することで、企業の経済的負担を軽減できます。


働きやすい職場環境を整える
外国人に転職されないためには、働きやすい職場環境の整備が必要です。
以下は、外国人が働きやすいと感じる環境の一例です。
- 母国の文化や宗教への配慮がある
- 定期的な面談を実施して悩みを聞く
- 就労面だけでなく生活面のサポートもする
- 外国人の能力やレベルにあわせた研修・教育を実施する
- 日本人スタッフと処遇や労働条件が同等に扱われている
- 日本人スタッフが事前研修を受けており、外国人に対して理解がある
外国人労働者が抱えそうな不安や不満を想定し、事前に対策を講じると転職リスクを下げられます。
「外国人向けの研修や教育の実施方法を知りたい!」という方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人教育の基本原則
- 在留期間における教育ロードマップ
- 実践的な教育のコツ
- よくある失敗例と対策 など
育成就労制度に関するよくある質問


最後に育成就労制度に関するよくある質問と回答をまとめます。
育成就労制度で外国人は何年働けますか?
育成就労の期間は3年間に定められています。
参考:厚生労働省|育成就労制度の概要
育成就労制度はいつから始まりますか?
育成就労制度のメリット・デメリットを把握して対策を考えながら外国人を受け入れよう


育成就労制度は、人材を柔軟に配置できたり、技能実習生よりも日本語能力の高い外国人の受け入れたりするメリットがあります。
その一方で、経済的負担や転職されやすい仕組みなどのデメリットも存在します。
デメリットの部分をよく理解しないまま外国人を雇用してしまうと、経費の予算オーバーや早期離職による採用コストの損失を招きかねません。
本記事で紹介したデメリットを解消するための対応策を参考に、制度を上手に活用して外国人材の受け入れを成功させましょう。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿