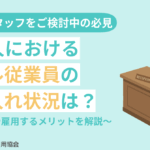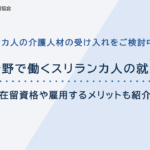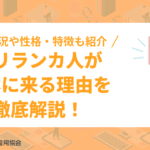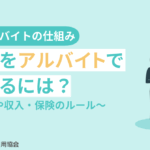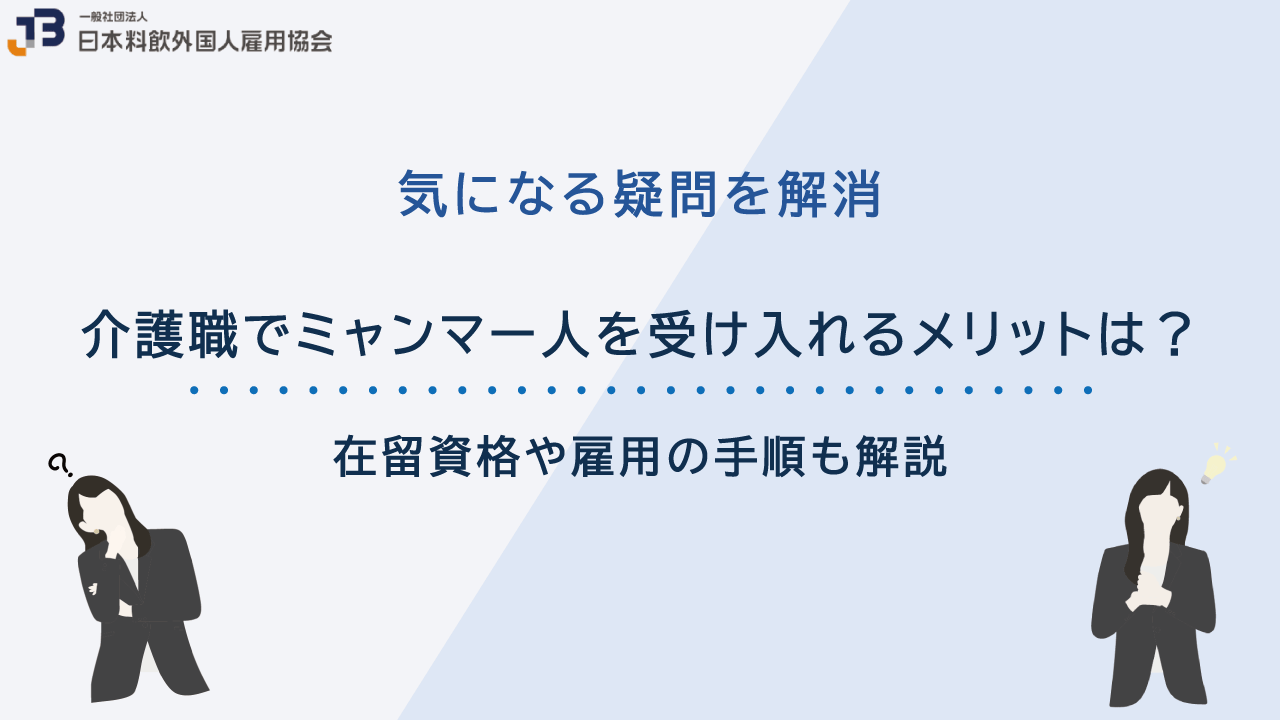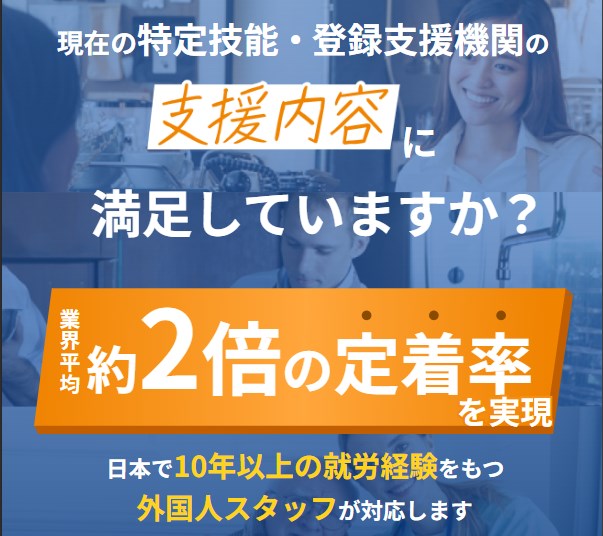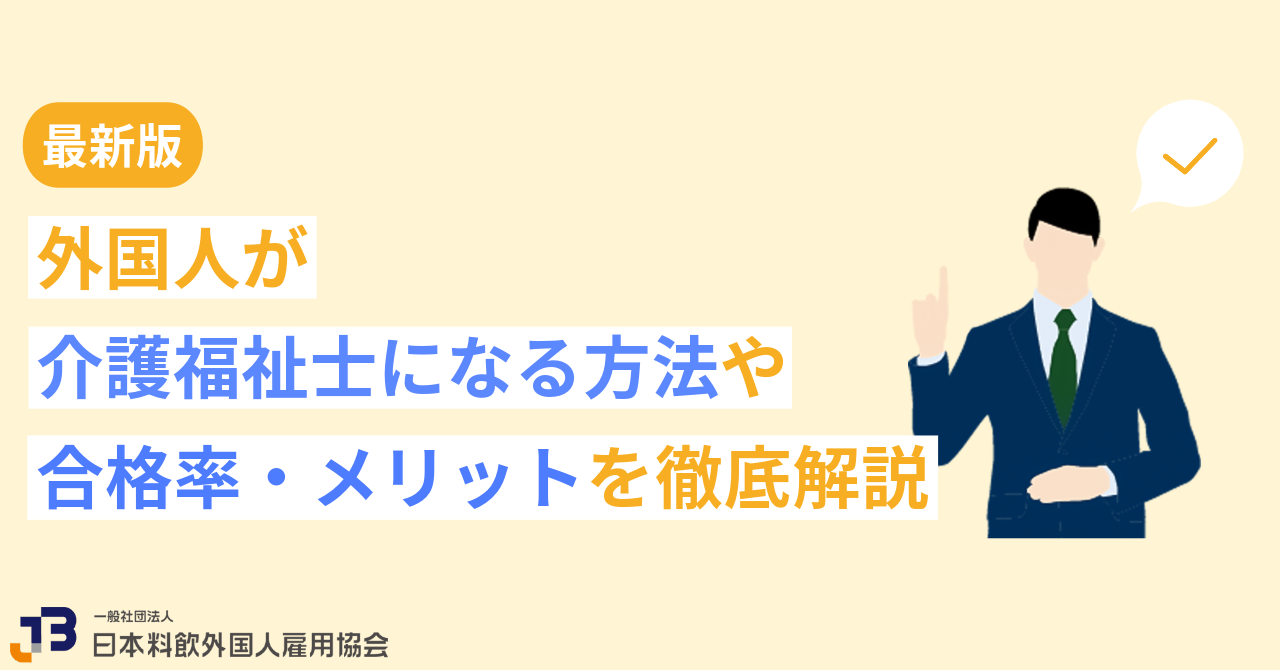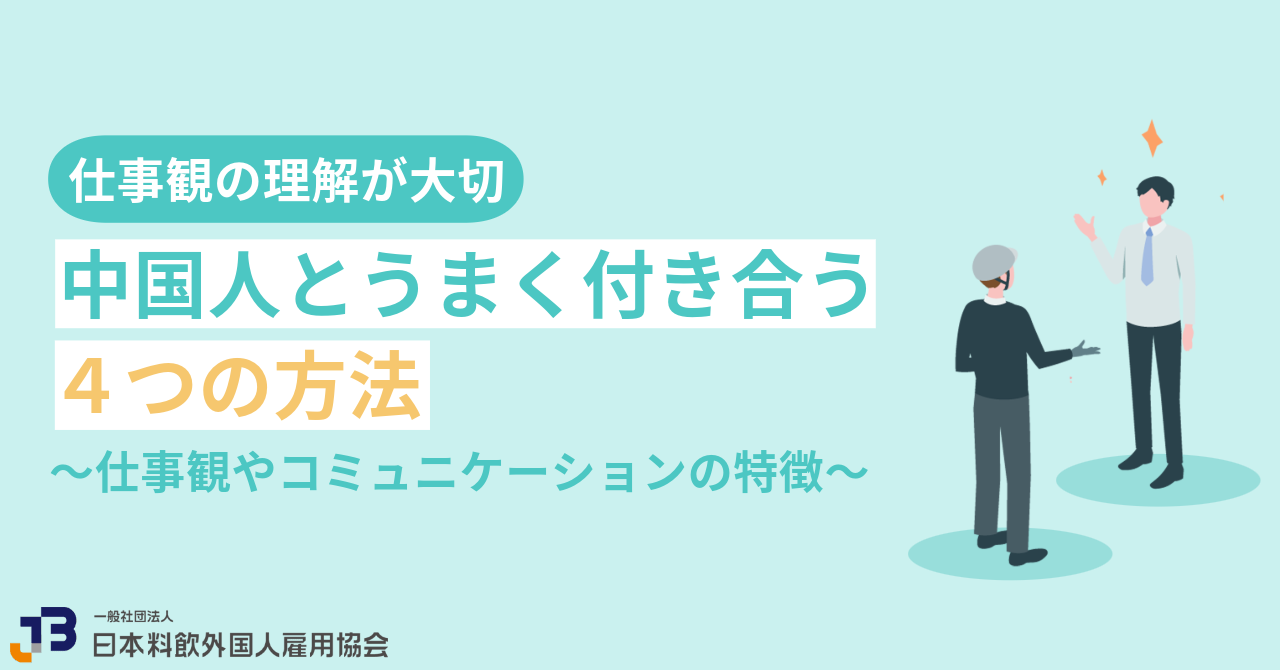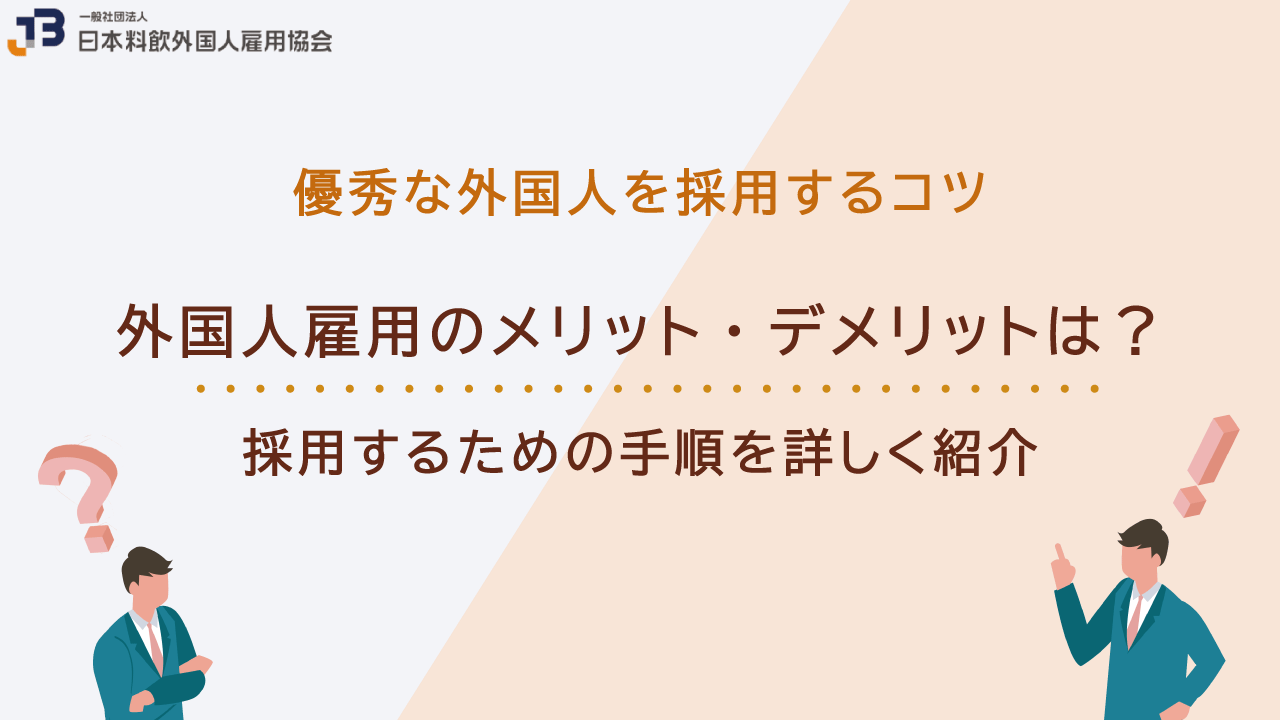「どれくらいのミャンマー人が日本の介護現場で働いているの?」
「ミャンマー人の国民性や文化的に介護職って向いてるの?」
「実際に受け入れる場合の在留資格や手続きの方法が知りたい」
このような疑問や不安を抱えていませんか?
少子高齢化が進む日本では、介護人材の確保が深刻な課題となっています。
その中で、ミャンマー人の介護人材が期待されています。ミャンマー人は、誠実で若い層の応募者が多く、文化的背景から介護職への関心が高いためです。
本記事では、日本で働くミャンマー人の就労状況や日本に来て働く理由を解説しています。ミャンマー人を受け入れるメリットや必要な在留資格、雇用する流れも紹介しているので参考にしてみてください。

この資料でわかること
- 訪問介護解禁の背景・概要
- 外国人材・事業者における要件
- 訪問介護における外国人材の受入れ手続き
- 訪問介護に外国人材を導入するメリット など
日本の介護現場で働くミャンマー人の就労状況

日本の介護現場で働くミャンマー人はどれくらいいるのでしょうか。
詳しくは後述しますが、ミャンマー人が介護職で働ける在留資格(日本に滞在し活動することが認められた資格)は「技能実習」「特定技能」「介護」の3つです。
その中で「特定技能」の在留資格を持つミャンマー人の就労状況データが確認できました。
以下は厚生労働省の資料に掲載されている、介護の特定技能外国人の国籍を示した表です。※国名をクリックすると関連記事にジャンプします
| 国籍 | 特定技能外国人在留者数 |
|---|---|
| インドネシア | 12,242人 |
| ミャンマー | 11,717人 |
| ベトナム | 8,910人 |
参考:厚生労働省|外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について
介護現場で働くミャンマーの特定技能外国人の数は約1.2万人で、インドネシアに次いで2番目に多いです。この結果から、ミャンマー人材への需要が高いことがわかります。
参考:厚生労働省|外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について
ミャンマー人を介護職に受け入れる3つのメリット

ミャンマー人は介護職に適した多くの特性を持っており、受け入れるメリットがあります。
主なメリットは以下の3つです。
- 真面目な国民性で信頼できる
- 日本語のスムーズな取得を期待できる
- 30歳前後の若い人材を確保できる
順番に見ていきましょう。
真面目な国民性で信頼できる
ミャンマー人は仏教を深く信仰する文化で育っているため「嘘をつかず誠実に行動すること」「人を思いやること」を重んじる傾向にあります。
とくに年長者や障がいのある方に敬意を持って接する姿勢が根づいており、介護の現場でも優しさが自然に発揮されます。
若い時から特に女性を中心に、病気の両親や祖父母を真剣に看病や世話をする習慣があります。
また、ミャンマーには教育課程では統一試験という厳しい制度があり、若い頃から努力を積み重ねている人も少なくありません。そのため、任された仕事に対して真摯に向き合い、責任を持って取り組む人が多いのも特徴です。
日本語のスムーズな取得を期待できる
ミャンマー語は日本語と語順や文法構造に共通点が多く、発音も似ているため、日本語学習への心理的なハードルが低いと言われています。
実際に短期間で日常会話を習得する人も多く、介護現場での業務や高齢者との会話にもスムーズに対応できることが期待されています。
 猪口 裕介
猪口 裕介外国人採用のネックとなる言葉の壁が低いため、施設側も安心して採用できる傾向にあります。
20代後半から30代前半の若い人材を確保できる
来日して介護現場で働くミャンマー人は若い年齢層の方が多い傾向にあります。
以下は、ミャンマー人の介護人材における年齢層に関するデータです。
| 年齢 | 割合 |
|---|---|
| 20~24歳 | 5.6% |
| 25~29歳 | 42.6% |
| 30~34歳 | 22.2% |
| 35~39歳 | 18.5% |
| 40歳以降 | 11.2% |
出典:株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所|外国人介護福祉士の活動実態に関する調査研究事業報告書
25〜29歳の人材が全体の4割を占めています。30〜34歳の年齢層とあわせると、全体の約65%が、20代後半から30代前半の若い人材となっています。
介護業務に必要な体力や継続的な学習への意欲を備えた人材が多いので、若い世代の確保は現場の活性化につながります。
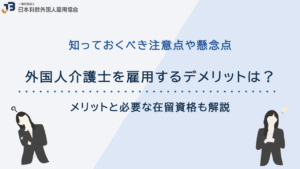
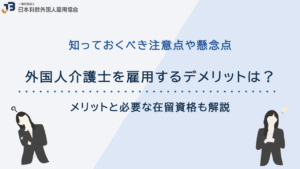
ミャンマー人が日本に来て介護職で働く理由


日本で介護職に従事する外国人の中でも、ミャンマー出身の方々は年々増加しています。その背景には、様々な理由が存在します。
ここでは、ミャンマー人が日本に来て介護職で働く理由を解説します。
主な理由は以下の3つです。
- 介護職への関心が強いから
- ミャンマーと日本の給与格差が大きいから
- 自国でクーデターが発生しているから
背景を知ることで、ミャンマー人に対する理解と信頼感が深まります。
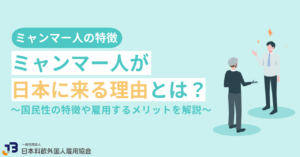
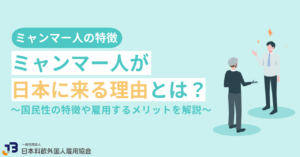
介護職への関心が強いから
ミャンマーでは、仏教的な価値観や他者への思いやりを重視する文化が根づいており、高齢者や身体が不自由な人を支える介護職は「徳を積む仕事」として捉えられています。
そのため、他国と比べても介護分野への関心が高く、介護職を第一希望とするケースが多く見られます。
以下のデータは、令和6年末時点で、特定技能1号の在留資格で日本国内に在留するミャンマー人の職種別の人数を示したものです。
| 職種 | 人数 |
|---|---|
| 介護分野 | 11,717人 |
| 外食業分野 | 8,561人 |
| 飲食料品・製造業分野 | 3,643人 |
| 合計 | 27,337人 |
出典:出入国在留管理庁|特定技能在留外国人数
全体の4割以上が介護分野で働いており、他業種と比べても圧倒的に多いことがわかります。介護職への志望度が高いことは、意欲的な人材を確保できるチャンスです。
また、採用する側にとっても安定した定着と長期雇用の面で大きなメリットです。
ミャンマーと日本の給与格差が大きいから
ミャンマーの平均的な給与水準は、アジア諸国の中でも著しく低いです。
以下はミャンマーとアジア主要国の給与水準を示した表です。
| 国名 | 中央値(ドル) | 平均値(ドル) |
|---|---|---|
| 中国 | 540 | 651 |
| マレーシア | 419 | 492 |
| ミャンマー | 121 | 164 |
※「中央値」は多くの人が受け取っている金額の目安「平均値」は全体の合計を人数で割った金額
出典:JETRO|新型コロナ禍2年目のアジアの賃金・給与水準動向
ドルを円換算(1ドル150円として換算)すると、ミャンマー人が受け取る給与の平均値は、約2万4千円です。他の国に比べて3分の1以下であることから、経済的な格差が大きいことがわかります。
日本の給与はアジア圏の中では高水準なので、安定した収入を得られる環境を求めて、ミャンマーを離れ日本の介護職を目指す人が増えています。
自国でクーデターが発生しているから
ミャンマーでは、2021年の軍事クーデター以降、政情不安が続き、各地で衝突や混乱が起きています。現在も国土の半分近くが紛争の影響を受け、国内避難民は350万人を超えているとされています。
さらに、1980年代から難民問題が続いており、100万人以上が国外に避難している状態です。
クーデターや難民問題が続いていることもあり、安全な環境で働きたいと考え、日本をはじめとする国外での就労を目指すミャンマー人が増えています。
介護職に限ったことではありませんが、日本は制度や受け入れ体制が整っており、安心して働ける国のひとつとされています。



中でも介護分野は、働く環境や将来の見通しが比較的安定しているため、ミャンマーの人に人気の職種です。
参考:週刊 経団連タイムス|人道支援が必要とされるミャンマー情勢


ミャンマー人が介護職に就ける在留資格|介護福祉士の資格を取得するタイミングも紹介


日本で介護職に就くには、いくつかの在留資格があります。
ミャンマー人が取得できる介護分野の在留資格は、以下の3つです。
- 技能実習
- 特定技能1号
- 在留資格「介護」
種類によって、働ける期間や業務の範囲が異なります。
介護福祉士の資格を取得する流れも紹介しているので、参考にしてみてください。
技能実習
技能実習は、介護を学びながら働ける在留資格です。対象は18歳以上で、将来的に母国で介護業務に従事する予定がある人に限定されます。日本の介護現場で実践的なスキルを身につけ、帰国後は自国で活かせる点が特徴です。
2025年の法改正により、一定の条件を満たす技能実習生は、これまで認められていなかった訪問系介護サービスにも令和7年4月1日から従事できるようになりました。
また、介護施設等で実務経験を3年以上積んだミャンマー人は、介護福祉士国家試験を受けられます。試験に合格できれば、在留資格を「介護」に切り替え、介護福祉士として継続して従事が可能です。
特定技能1号
特定技能は、日本の人材不足解消を目的とした在留資格です。資格を申請する要件に、介護分野における技能評価試験と日本語能力試験の合格が含まれているため、即戦力となるミャンマー人を確保できます。
技能実習と同じく法改正によって、令和7年4月21日から一定の条件を満たす特定技能外国人は訪問系サービスへの従事が認められました。
特定技能外国人の場合も、実務経験を3年以上積めば、介護福祉士試験の受験資格を得られます。見事試験に合格できれば、在留資格「介護」に切り替えて、介護福祉士として介護職で活躍できます。


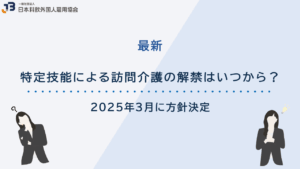
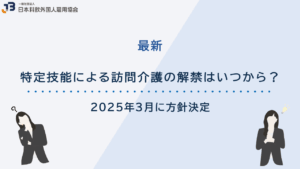
「訪問系サービスの解禁について理解を深めたい」という方に向けて、特定技能制度 訪問介護解禁 導入スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 訪問介護解禁の背景・概要
- 外国人材・事業者における要件
- 訪問介護における外国人材の受入れ手続き
- 訪問介護に外国人材を導入するメリット など
在留資格「介護」
「介護」は、介護福祉士の国家資格取得者が対象の在留資格です。
国家試験の受験資格を得るためには、日本国内の養成校や専門学校などで所定のカリキュラムを修了するか、技能実習・特定技能の在留資格で実務経験を3年以上積む必要があります。
これらの過程を経た人材がこの資格を持つため、介護分野の知識と技術が高いミャンマー人を雇用できます。
ほかの在留資格と異なり、在留期間の上限がないため、長期的な雇用が可能です。


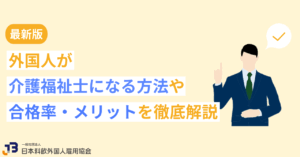
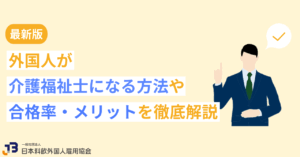
外国人を雇用する際の注意点


介護分野で外国人材を受け入れる際は、国民性や文化的背景を把握しての対応が求められます。
適切な配慮を欠くと、信頼関係を損ない、離職につながるリスクがあるためです。
以下の表に、外国人材における性格の一例と関わり方の配慮をまとめました。
| 外国人材の性格の一例 | 関わり方の配慮 |
|---|---|
| プライドが高い人もいる | 自分の行動に対する責任感が強いので、文化や習慣からの違いがあった場合の注意は個別に行うなど工夫しましょう。 |
| 遠慮しやすい | 職場に慣れるまでは時間がかかり、意見を言えなくなる方もいます。 ストレスがたまる前に個別に話をするなど悩みを聞きとる機会を作りましょう。 |
| あいさつの文化が異なる | 日本とあいさつの習慣が違っていることも多く、無言ですれ違うことが失礼に当たらないと考えている国もあります。 本人にも、施設内の方にも相互に理解を促して環境を整えていくことで定着に繋がります。 |
こうした点に配慮することで、文化や価値観の違いによる誤解やトラブルを防ぎ、利用者にとってもスタッフにとっても安心できる職場環境をつくれます。
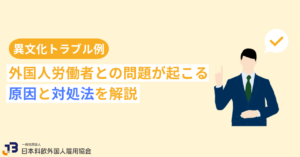
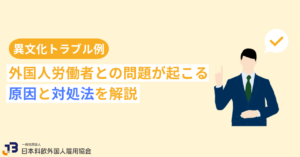
「外国人労働者に適した教育・研修方法が知りたい!」という方に向けて、外国人の教育・研修のコツ・注意すべき落とし穴の資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人教育の基本原則
- 在留期間における教育ロードマップ
- 実践的な教育のコツ
- よくある失敗例と対策 など
【手順】介護職でミャンマー人を採用する流れ


外国人介護人材を雇用する際は、主に「海外にいる段階で契約するケース」と「すでに日本国内に在留している人材と契約するケース」があります。
今回は、日本国内で契約を結ぶ場合に焦点を当てて流れを解説していきます。
- 1.人材を募集する
- 2.面接を実施する
- 3.雇用契約を結ぶ
- 4.在留資格変更申請をする
- 5.入社後のフォローも行う
それぞれのステップで押さえておきたいポイントを詳しく見ていきましょう。
1.人材を募集する
まずは人材を募集します。
ミャンマー人を含む外国人を募集する代表的な方法は以下のとおりです。
- 求人サイトに求人を掲載する
- 人材紹介会社に依頼する
- 専門学校や大学に求人を出す
- SNSで募集する
- 自社のホームページに人材募集の情報を掲載する
自社に合う方法を探して募集してみてください。
効率的な人材確保を希望するなら人材紹介会社の利用がおすすめです。
その中でもミャンマー人の就労支援に強い会社を選ぶと良いでしょう。国民性や文化を熟知しているため、マッチング精度の向上が期待できます。
2.面接を実施する
書類選考を通過したら、対面またはオンラインでの面接を実施します。
面接の際には必ず在留カードを提示してもらい、在留資格や働ける内容に問題がないかを確認してください。
また、特定技能外国人を採用する場合は、技能評価試験と日本語試験に合格していることが必要条件となります。



事前に合格証明書の確認も忘れずに行いましょう。
3.雇用契約を結ぶ
面接を経て採用が決まったら、次は雇用契約を正式に結びます。契約書の作成は必須であり、口頭だけの取り決めはトラブルの原因になるため避けましょう。
また、外国人雇用においては、日本人と同等以上の待遇であることが前提条件です。賃金や労働時間、雇用条件が適正なのかを法律と照らし合わせ、しっかりと確認しましょう。
契約内容に誤解が生じないよう、書面は本人が無理なく読み取れる言語で用意することが大切です。意味を理解せずに署名させてしまうと、誤解や契約上のトラブルを招いてしまうからです。
雇用契約を結ぶ際には、通訳を交えるなどして、納得したうえで契約できる環境を整えましょう。
4.在留資格変更申請をする
雇用契約を結んだら、在留資格変更を申請します。
具体的な手順は以下のとおりです。
- 必要書類を収集する
- 申請書を作成する
- 出入国在留管理局で申請する
- 審査結果の通知を確認する
- 新しい在留カードを受け取る
資格変更が完了するまで、就労はできません。審査には1~2ヶ月ほどかかるので、スケジュールに余裕を持ち、確実に申請を進めましょう。
在留資格の公的な手続きは、申請取次行政書士に依頼すると申請が的確かつスムーズに進みます。申請取次行政書士は外国人雇用の公的手続きに精通した専門家です。
どの行政書士に委託すれば良いのか迷ったら弊社と連携する「FES行政書士法人」のご利用をご検討ください。外国人就労者・海外人材に特化した行政書士法人で、豊富な実績とノウハウを持っています。
\メール相談は無料で対応/
▲お問い合わせはページ下部のフォームから
5.入社後のフォローも行う
外国人介護人材が安心して業務に取り組めるよう、入社後も丁寧なフォローが欠かせません。
以下は、ミャンマー人が安心して働くために必要なサポート内容の一例です。
- 業務の流れや職場のルールに慣れてもらうために社内研修を実施する
- 介護現場で必要な言葉を習得できるよう日本語学習をサポートする
- 悩みを早期に把握するためにも定期面談の機会を設ける
これらのサポートを継続することで、ミャンマー人材の定着率向上と職場環境の改善が期待できます。
「採用手順の理解をさらに深めたい」という方に向けて、外国人雇用スタートガイドの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。


この資料でわかること
- 外国人採用の意義
- 外国人雇用のメリット
- 外国人採用スタートの5ステップ
- よくある課題と解決策
ミャンマー介護人材の受け入れは「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください


「ミャンマーの介護人材を受け入れたいが、自社で対応できるか不安」
このようにお悩みの方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護業界の就労支援に強い人材紹介会社です。主にアジア諸国の人材紹介を手がけており、その中でもミャンマー人の支援実績が豊富です。
登録支援機関でもあるため、介護の特定技能1号外国人における支援計画書の作成や義務的支援の実施もサポートしています。
外国人労働者の受け入れに関する各種サポートはもちろん、在留資格の手続きや書類対応が必要な場面では、外国人雇用に強い「FES行政書士法人」との連携により、法的な面までしっかり対応可能です。
無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
\業界平均約2倍の定着率を実現!/
ミャンマーからの介護人材受け入れを前向きに検討しよう


ミャンマー人にとって介護はもっとも人気のある職種で、多くの人が日本での安定した就労や将来のキャリア形成を目的に志望しています。
介護人材としてミャンマー人の受け入れを検討している方は、本記事を参考に、自社に合った体制づくりを進めていってください。
とはいえ「ミャンマー人の受け入れにかかる手続きや指導体制に不安がある」という方もいるでしょう。
このように悩んだら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。
弊社は、介護分野の就労支援に強みを持ち、採用支援と職場定着に注力しています。日本語能力や人柄、現場適性などを重視したマッチングにより、ミスマッチの少ない人材確保を実現できます。また、「FES行政書士法人」と連携しているため、各種公的手続きも円滑に対応可能です。
無料相談を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
監修者プロフィール


- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長
- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。
最新の投稿